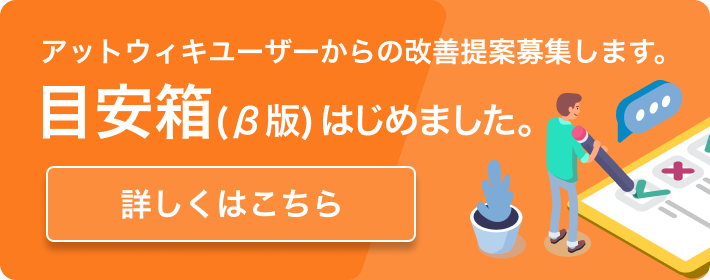知るも知らぬも大阪の席
お話の中のおいしいモノ
最終更新:
kyo
-
view
特に食べ物がテーマじゃなくても、小説の中にはいろいろな食べ物が出ててくる。
それぞれ面白かった小説をその中のメニューで切り取っておいたら備忘録にならないかな、と思って書いてみてます。
それぞれ面白かった小説をその中のメニューで切り取っておいたら備忘録にならないかな、と思って書いてみてます。
ローストビーフとデリア風ローストポテト
| ちょっとダメな男たちを描かせたらぴか一のニック・ホーンビィが、珍しく女性の視点で書いた本。原題は「How to be good」 主人公「私」(ケイティ)の皮肉屋の夫は、「私」の浮気がきっかけで「いい人」になってしまう。この「いい人」、というのは極めてシニカルな表現で、簡単に言うと「偽善者」である。自分のことは何一つできていないのに正論ばかり言う人。本人自身がそのことに気付いていないからそれがまたたちが悪い。 表題のメニューは、「私」の両親が遊びに来た時に、二人の子供たちと自分たち夫婦と両親の3世代で食べようと思って用意したお決まりのロースト料理。それを取り分けて、グレービーソースを作ろうとしていた夫ディヴィッドが、いきなりその料理をやっぱりホームレスや貧しい人たちに分け与えたい、と言ってルクルーゼのお鍋に詰め込み出す。「僕たちはこんな贅沢なものを食べているのに彼らは何も食べていないじゃないか、分け与えてあげないきゃ。」と。 ま、こんな夫が家にいたらある意味でホラーである。夫のしでかす数々の出来事に対して腹が立つたびに、本当は自分はとても悪い人間なのだろうか、と時々自問自答しちゃう混乱した主人公ケイティの心情が実にリアルに描かれていて面白い。 |
小エビのグリエとマンサリーニャ
| 主人公マリアと夫のピエールと娘のジュディットと若くて美しいクレール。4人はスペイン旅行中。マリアは夫と美しい友人クレールが実は強く惹かれあっている、という確信を持っている。彼女は二人が一緒にいるところを想像せずにはいられなくって、同時にお酒を飲まずにはいられなくなる。旅行の間中、彼女はこのマンサリーニャという辛口のシェリー酒を飲んでいる。標題のメニューは、物語の盛り上がりも落ち着いたラストの方、マドリッドへ行く途中に立ち寄った小さな村で、お昼にオーダーしたもの。クレールが小エビのグリエ食べる時に、殻を噛み砕く音がマリアまで聞こえる。うーん、実に生々しい。食事をする行為はなぜかとてもエロティックな時がある。 |
油っこいピザとコーラ
| 私が今まで読んでいた小川洋子さんの小説のイメージからは予想外のテーマだった。実はあらすじも読まずに買ったのだが、電車の中で読むとちょっと恥ずかしいかも知れない倒錯的内容である。標題のメニューは主人公の少女と変な翻訳家のおじさんがとあるレストランで悲しくなるくらいムゲな扱いを受けた後に、別のお店で食べたメニュー。指がべたべたに汚れるくらいの油っこいピザ、ってところが、この作家さんらしい「哀しい残酷さ」が出ていて面白い。 |
オムレツ・仔羊のローストインゲン豆添え・桃の赤ワイン漬け
| ちょっと風変わりな「私」が数々の回想と現実を織りまぜながら、詳細な料理について語っていくストーリー。表題の3つのメニューは「私」が勧める春のメニューの中の一品。小説の舞台はプロヴァンスがメインなのだが、このメニューはブルターニュのとあるレストランの自慢メニューだそうだ。ブルターニュの風景を描いている部分が個人的に懐かしく興味を覚えた。 小説の中では「オムレツ」がよく登場するのだが、実はこのストーリーの中でオムレツはとても大切な役割を果たしている。最後のメニューは「野山で取って来たきのこのオムレツ」。最後の最後でストーリーは思わぬ方向へドライブしていく。「そうきたか!」と驚くこと間違いなし。 実に面白くおいしい本だと思う。 |
網の上で焼いたシンプルなグリルサーディン
| 死の床に瀕した高名で厳格な料理評論家が、生涯最高の味はなんだったんだろう、と数々の料理を回想するお話。そこに様々な人間模様が絡んでくる。表題のメニューは彼がまだ美食家になりきる前の子供の頃、おじいちゃんが作ってくれたメニュー。これもまた舞台はブルターニュ。季節は夏。夏の間だけブルターニュに祖父母が家を借りていたそうだ。網の上で焼かれたサーディンの皮が焼けてぷくぷくと膨れ上がり、網から取り上げると半分くらい皮がめくれてしまって、白い身が出てくる。その身を骨から上手に取り外して口に運ぶ。うーん。すっきりとした白ワインがすすみそうだ。 他にも「ツノ」という名人の板前がいる「オシリ」という不思議な日本料理屋での体験などなど、美食エピソードがいろいろ出てくる。しかし、結果的に彼が最後にたどりついた味は・・・ テンポ良く読み進められる軽い小説だが、「幸せ感」なんかについてもそれなりに考えさせられるところもある。 さて、私が最後に食べたい味は何だろう。 |
香草入りオムレツとレモネード
| 1930年代のポルトガルの独裁政権下で、小さな新聞社(夕刊しか出さない)の文芸担当の真面目で太った編集長が、一人の青年に出会ったばっかりに知らず知らずのうちに政治運動らしきものに巻き込まれて行く。心臓も弱く、最愛の妻をなくしてからは人生の楽しみとてたいして持たない彼が、唯一、やめられなかったのが、香草入りのオムレツと砂糖たっぷりのレモネード。オムレツを食べることは彼の心臓にもいい食習慣とは言えず、医者にも黙っていたりする。この香草入りオムレツとレモネードは緊迫したストーリー展開の中で、随所に登場する。一人の人間ではどうしようもない政治的な大きなうねりの中で、オムレツとレモネードは、ただペレイラの心臓だけを脅かす小さな個人的欲求の象徴として描かれているようで、非常に印象に残る。 この小説を読んでから、私は何度となく、チーズのたっぷり入った香草入りオムレツを作って食べた。チーズとバジルと半熟卵が口一杯にジューシーに広がる時、タブッキの描いた穏やかならぬ世界の中で善良なペレイラの追いつめられて行く状況がフラッシュバックする。彼はリスボンの街角のカフェでどんな気持ちでこのオムレツを食べたのか。 |
ソーセージとそのグレービーソースがたっぷりかかった目玉焼き
| 「ティファニーで朝食を」のカポーティーの処女長編。お母さんを亡くした主人公ジョエルが、初めて会う本当のお父さんの不思議なお屋敷で過ごす日々を描いたもの。 世の中はなんだか不思議でちょっと怖いもの、時々楽しく、そしてままならない、という少年の目線で描かれている。 標題のメニューは彼が初めてこのお屋敷にやって来た時に、出された食事。最後にとうもろこしのパンでグレービーソースをぬぐって食べるシーンがある。実においしそうだ。初めての環境に放り込まれて心細くても、やっぱりお腹はすくんだなぁ。と少しほっとしたシーンである。 とはいうものの、全編の中でおいしそうなメニューが出てくるシーンはこれ以外ほとんどない。 |
木の芽の香りの豆腐田楽
| 食べ物や食べるシーンが見せ場になっている落語集。標題はこの中の「田楽喰い」。関西のおでんはもともと煮込みではなく、味噌を付けて焼く田楽。で、煮込みおでんは関東のものだから関東煮き、と区別していたそうだ。 上方落語によく出てくる、あんまり仕事もせずぷらぷらしているのんきな裏長屋の住人たちが寄り集まって、お金はないけどお酒飲みたいなぁ、と。その中の一人の人のお兄さん(この人はまともでちょっとお金持ちらしい)の家にたくさんお酒があるから、ちょっとみんなでタダ酒飲みに行こう、ってことで、一知恵絞る。ま、早い話がお兄さんを騙すのである。落語はたいてい騙されたお兄さんがかわいそう、って方向にはならなくて、みんなが機嫌よく、豆腐田楽を食べながらお兄さんのお酒を飲むことになる。で、「ん」が付く言葉を言ったら田楽食べられることにしよ、と子供の遊びみたいなことしてお酒をまわし飲み、そのままの勢いで「下げ」が付く。 噺家さんがこれをやると豆腐田楽が実においしそうに思えるのである。 他に16編。 |