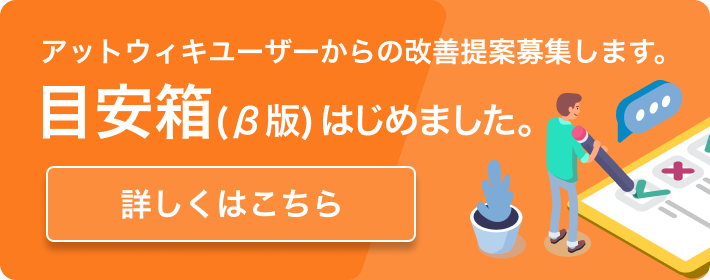風紀委員会SS第一話
「あなたね、一体どういうつもりなの!?」
麗しい少女の、その容姿とは不釣り合いな怒声が、風紀委員会室に響く。彼女、黒姫 射遠(くろひめ-いおん)は、立ち上がり、机に両手をついたまま、目の前の少女を問い詰めている。男子生徒の含み笑いを除くと、しんと静寂に包まれる一室の中、黒姫 射遠と相対するその少女、清々那 帰莢(すがたな-きさや)はと言うと、その場の空気を一切意に介する様子もなく、無愛想に彼女を見返していた。
一触即発、その光景を見ていた一年生委員たちの誰もが、その二人の様子を心中でそう表現していた。
怒れる虎に、それを見下ろす龍(不気味な存在)、そのおどろおどろしい構図に、二年生委員でさえ、そのほとんどが、息を呑んでいた。唯一、汚水(よごみず) ぎゃん――彼だけがクスクスと、不敵な笑みを浮かべながら、その様子を見守っている。
三学期に入り、三年生が事実上引退してしまった今、実質的に風紀委員の次期委員長は「黒姫 射遠」だと言うのは、誰もが認めるところであった。
黒姫 射遠の実力は、誰もが認め、その人望も大きかった。
もし、これが風紀委員内の単なる派閥争いであるなら、この場の誰もが、黒姫 射遠の味方となり、彼女を擁護していただろう。
しかし、今回は状況が違った。
「なんのつもりか知らないけど、どうして反撃しないの? なんであなたは見てるだけで、いつもいつも、被害が広がるのを黙って見過ごしているの? 相手はあなたを殺そうとしてるのよ!?」
黒姫 射遠は、正義感が強い少女だった。
麗しい少女の、その容姿とは不釣り合いな怒声が、風紀委員会室に響く。彼女、黒姫 射遠(くろひめ-いおん)は、立ち上がり、机に両手をついたまま、目の前の少女を問い詰めている。男子生徒の含み笑いを除くと、しんと静寂に包まれる一室の中、黒姫 射遠と相対するその少女、清々那 帰莢(すがたな-きさや)はと言うと、その場の空気を一切意に介する様子もなく、無愛想に彼女を見返していた。
一触即発、その光景を見ていた一年生委員たちの誰もが、その二人の様子を心中でそう表現していた。
怒れる虎に、それを見下ろす龍(不気味な存在)、そのおどろおどろしい構図に、二年生委員でさえ、そのほとんどが、息を呑んでいた。唯一、汚水(よごみず) ぎゃん――彼だけがクスクスと、不敵な笑みを浮かべながら、その様子を見守っている。
三学期に入り、三年生が事実上引退してしまった今、実質的に風紀委員の次期委員長は「黒姫 射遠」だと言うのは、誰もが認めるところであった。
黒姫 射遠の実力は、誰もが認め、その人望も大きかった。
もし、これが風紀委員内の単なる派閥争いであるなら、この場の誰もが、黒姫 射遠の味方となり、彼女を擁護していただろう。
しかし、今回は状況が違った。
「なんのつもりか知らないけど、どうして反撃しないの? なんであなたは見てるだけで、いつもいつも、被害が広がるのを黙って見過ごしているの? 相手はあなたを殺そうとしてるのよ!?」
黒姫 射遠は、正義感が強い少女だった。
■■■■■■
彼女が、この学園に転入し、風紀委員となったとき、すでに「清々那帰莢」という少女は、風紀委員会に所属しており、彼女にとっては先輩であった。
清々那 帰莢――彼女は、初めこそ黒姫 射遠の眼には、清々那 帰莢は、聖人のようにも見えた。
常に、自分よりも早く現場に駆けつけ、どれだけ対象に怪我を負わせられても、仲間が駆け付けるまで決して無抵抗を貫き、対象の気を引く姿に、ある種の尊敬の念を抱いたこともあった。
しかし、彼女のそんな思いも、ある事件によってあっけなく裏切られる。
あの卒業式、山乃端一人が殺された日、生徒会や番長グループが、犯人を特定するべく動いていたとき、風紀委員会も彼らに協力し、山乃端一人を殺害した犯人を捜索することとなった。
犯人の逃亡の可能性も考えられ、捜査範囲は、学区外にまで広がっていた。この状況で風紀委員までも、学園内から目を離せば、どんなことになるかは、誰もが容易に想像できた。
学園内が疑心暗鬼となる中、より学園の風紀を監視すべきだという声も上がったが、黒姫 射遠は、山乃端一人の犯人を捕まえることを優先させた。下手に監視を強めては、生徒たちの不安をいたずらに高めるだけであり、それよりも、一刻も早く犯人を特定し、逃亡を許さないことが、最終的に学園を元に戻す近道だと考えたからだ。
しかし、それでも生徒会と番長グループだけでなく、風紀委員会まで動くとなると、学園の風紀は緩んでしまうのは、必然である。
だから、黒姫 射遠は、清々那 帰莢に学園の監視を頼んだ。常に現場にいち早く駆けつける彼女なら、手薄になった学園内をカバーし、何か異常が起きたら、すぐにこちらに報告できると期待したからだ。
清々那 帰莢は、何も言わず了承した。その時は、彼女の無愛想も、仕事に徹する生真面目さに感じ、頼もしくも黒姫 射遠は思った。
だが、それが誤りだったと気付くのに、大して時間はかからなかった。
――学園内の風紀が最も乱れた日。それは、山乃端一人の死亡日という意味合いだけでなく、風紀委員会の名誉に関しても最も恥ずべく日となった。
誰もが疑心暗鬼となり、互いに互いへ不信の眼差しを向けあう中、学園内で暴動が起こる。これは、やはり必然的であった。
生徒の誰もが、休戦協定を支持していたわけではない。それももちろん、彼らは熟知していた。それを封じていた山乃端一人の死が、どのような事態を呼ぶかも。すべて想定の範囲内。だが、一年もの平和は、番長グループ・生徒会、彼らだけでなく風紀委員会にまでも、甘く淡い期待を抱かせるには充分なブランクだった。
清々那 帰莢――彼女は、初めこそ黒姫 射遠の眼には、清々那 帰莢は、聖人のようにも見えた。
常に、自分よりも早く現場に駆けつけ、どれだけ対象に怪我を負わせられても、仲間が駆け付けるまで決して無抵抗を貫き、対象の気を引く姿に、ある種の尊敬の念を抱いたこともあった。
しかし、彼女のそんな思いも、ある事件によってあっけなく裏切られる。
あの卒業式、山乃端一人が殺された日、生徒会や番長グループが、犯人を特定するべく動いていたとき、風紀委員会も彼らに協力し、山乃端一人を殺害した犯人を捜索することとなった。
犯人の逃亡の可能性も考えられ、捜査範囲は、学区外にまで広がっていた。この状況で風紀委員までも、学園内から目を離せば、どんなことになるかは、誰もが容易に想像できた。
学園内が疑心暗鬼となる中、より学園の風紀を監視すべきだという声も上がったが、黒姫 射遠は、山乃端一人の犯人を捕まえることを優先させた。下手に監視を強めては、生徒たちの不安をいたずらに高めるだけであり、それよりも、一刻も早く犯人を特定し、逃亡を許さないことが、最終的に学園を元に戻す近道だと考えたからだ。
しかし、それでも生徒会と番長グループだけでなく、風紀委員会まで動くとなると、学園の風紀は緩んでしまうのは、必然である。
だから、黒姫 射遠は、清々那 帰莢に学園の監視を頼んだ。常に現場にいち早く駆けつける彼女なら、手薄になった学園内をカバーし、何か異常が起きたら、すぐにこちらに報告できると期待したからだ。
清々那 帰莢は、何も言わず了承した。その時は、彼女の無愛想も、仕事に徹する生真面目さに感じ、頼もしくも黒姫 射遠は思った。
だが、それが誤りだったと気付くのに、大して時間はかからなかった。
――学園内の風紀が最も乱れた日。それは、山乃端一人の死亡日という意味合いだけでなく、風紀委員会の名誉に関しても最も恥ずべく日となった。
誰もが疑心暗鬼となり、互いに互いへ不信の眼差しを向けあう中、学園内で暴動が起こる。これは、やはり必然的であった。
生徒の誰もが、休戦協定を支持していたわけではない。それももちろん、彼らは熟知していた。それを封じていた山乃端一人の死が、どのような事態を呼ぶかも。すべて想定の範囲内。だが、一年もの平和は、番長グループ・生徒会、彼らだけでなく風紀委員会にまでも、甘く淡い期待を抱かせるには充分なブランクだった。
――それほど大事には至らないだろう。
この一年、さほど大きな小競り合いもなく、番長グループと生徒会の協力関係は続いている。大きな戦力のほとんどは、きちんと管理され、武器庫に仕舞われているに等しい状態だった。
だから、それほど大事にはならない。そう彼らは願った。だからこそ、風紀委員会も清々那 帰莢を含むほんの二、三人を残し、学園を出払った。
だが、この一年のブランクは、厳しい監視の元、抑圧され、猫を被らざるを得ない状況に置かれていた一部の生徒の、鬱憤を膨らませるのにも、やはり充分な期間だった。
このような、絶好の機会に、彼らが動き出さないはずがなく、彼らは、その混乱に乗じて、一斉に暴発した。
彼らは、残っていた風紀委員を処理すると、学園内にデマを流布した。その内容は、番長が休戦協定を破棄し、生徒会はハルマゲドンを声明したというものであった。
かつての争いを忘れてしまった者たちがいれば、逆にトラウマとなって残り、苦しみ続けている者たちもいる。山乃端一人が殺された混乱の中、そのデマを真に受けた者たちは、一年前の争いをフラッシュバックさせ、パニックに陥った。
一方でデマを流布した者たちは、それを笠に非道を尽くした。それは、快楽と暴力が蔓延し、非道がまかり通り、弱者は虐げられる、まさに地獄絵図と化していた。一時とはいえ、学園内は阿鼻叫喚に包まれた。
そんな中、清々那 帰莢は、その様子をただ見ているだけだった。自分と同じように学園に残った他の風紀委員のメンバーが、陰で殺されていくのも、黙って見ていた。
清々那 帰莢は、忌々しげに、残虐を繰り広げるものたちを、凍りつくような眼差しで、何もせず、ただ、じっと見ているだけだった。
虐げられていた生徒たちの中には、清々那 帰莢のその態度こそ、他の何よりも冷酷に感じるものいた。
悲鳴が響き渡り、物が宙を行き交う。アルコールが廊下を浸し、大麻の煙が校舎内のあちことで立ち込める中、彼女は自らに迫る危険に対しては、それなりの動作をして見せたが、他の誰がどうなろうと知るところではないという様子だった。
彼女は全てを"監視"するのみに止めた。それは、単なる傍観と言われても仕方のない類のものだった。
ある女子生徒は、清々那 帰莢に助けを求めた。ある男子生徒は、彼女の前で、非道を尽くした。しかし、彼女は、軽蔑のまなざしを向けるだけだった。まるで、ゴキブリの交わりでも見るように、触れることにすら、気持ち悪さを抱いているようであった。
だから、それほど大事にはならない。そう彼らは願った。だからこそ、風紀委員会も清々那 帰莢を含むほんの二、三人を残し、学園を出払った。
だが、この一年のブランクは、厳しい監視の元、抑圧され、猫を被らざるを得ない状況に置かれていた一部の生徒の、鬱憤を膨らませるのにも、やはり充分な期間だった。
このような、絶好の機会に、彼らが動き出さないはずがなく、彼らは、その混乱に乗じて、一斉に暴発した。
彼らは、残っていた風紀委員を処理すると、学園内にデマを流布した。その内容は、番長が休戦協定を破棄し、生徒会はハルマゲドンを声明したというものであった。
かつての争いを忘れてしまった者たちがいれば、逆にトラウマとなって残り、苦しみ続けている者たちもいる。山乃端一人が殺された混乱の中、そのデマを真に受けた者たちは、一年前の争いをフラッシュバックさせ、パニックに陥った。
一方でデマを流布した者たちは、それを笠に非道を尽くした。それは、快楽と暴力が蔓延し、非道がまかり通り、弱者は虐げられる、まさに地獄絵図と化していた。一時とはいえ、学園内は阿鼻叫喚に包まれた。
そんな中、清々那 帰莢は、その様子をただ見ているだけだった。自分と同じように学園に残った他の風紀委員のメンバーが、陰で殺されていくのも、黙って見ていた。
清々那 帰莢は、忌々しげに、残虐を繰り広げるものたちを、凍りつくような眼差しで、何もせず、ただ、じっと見ているだけだった。
虐げられていた生徒たちの中には、清々那 帰莢のその態度こそ、他の何よりも冷酷に感じるものいた。
悲鳴が響き渡り、物が宙を行き交う。アルコールが廊下を浸し、大麻の煙が校舎内のあちことで立ち込める中、彼女は自らに迫る危険に対しては、それなりの動作をして見せたが、他の誰がどうなろうと知るところではないという様子だった。
彼女は全てを"監視"するのみに止めた。それは、単なる傍観と言われても仕方のない類のものだった。
ある女子生徒は、清々那 帰莢に助けを求めた。ある男子生徒は、彼女の前で、非道を尽くした。しかし、彼女は、軽蔑のまなざしを向けるだけだった。まるで、ゴキブリの交わりでも見るように、触れることにすら、気持ち悪さを抱いているようであった。
黒姫 射遠の元に学園内の異常が知らされたのは、暴動が起こってから二、三時間が経過した後であった。
その知らせも、黒姫 射遠が風紀委員同士の連絡のために使っている携帯電話へではない、あくまで私的に使っているものへ、その報は入った。
学園全体に暴動が広がったのが、その十分後である。
黒姫 射遠を筆頭に風紀委員会が戻ってきたとき、一部の生徒が引き起こしたこととはいえ、そこは休戦協定が結ばれる前の、ハルマゲドン真っ只中の学園を彷彿とさせずにはいられないほど、学園は荒んでいた。
番長グループと、生徒会も駆けつけ、暴動はものの十分で鎮圧されたが、生徒たちの間に生じた「亀裂」は、致命的であった。
事はすぐに鎮圧されたとは言え、風紀委員が、手薄となった学園をまかされており、学園内には風紀委員の人間が残っていた。そのうち一名は、その光景を終始見ていただけという話だ。これを未然に防ごうとせず、さらには事態を看過していたことは重大であり、風紀委員会の責任問題となった。その結果、風紀委員会は、その発言権は急速に縮小させられた。
黒姫 射遠は、清々那 帰莢を恨んだ。そして、彼女を信頼した自分が情けなく、悔しかった。
だが、そのような惨劇のただ中にいて、清々那 帰莢も決して無事ということはなかった。彼女は、普通の人間はもちろん、魔人ですら、死んでいても可笑しくないような深手を負いながら、事の勃発から鎮圧までを、平然と突っ立ったままであったと言う。
殺しかねない勢いで、手当を受けていた清々那 帰莢のいる保健室の扉を叩いた黒姫 射遠でさえ、彼女の傷を見て、その怒りが引いてしまうほど、彼女の負傷は常軌を逸していた。
それは間違いなくただの人間にとって死傷と成り得るものであった。
頭皮はぱっくりと裂け、頭蓋骨の中身が垣間見える頭部。半分閉じられた瞼から、流れ落ちる赤黒い血の塊。そして、体の半分にも至る火傷。目につくものだけでも、その一つ一つが間違いなく重傷に違いがなかった。
そのくらいじゃ人間は死なない。そう言うのは簡単だが、実際にその姿を見たものにとって、その姿は、"生き物"ではなく、単なるグロテスクなオブジェクトであって欲しいと、そう願わずにはいられないほど、その姿は筆舌し難いものであった。
黒姫 射遠など、それなりの能力を持った魔人なら、それで彼女についてある程度合点はいく。だが、「凡百の生徒」は、その傷が日を増すごとにみるみると、跡形もなく再生していくのに、言葉にできない恐怖を、感じてしまっていた。
それは、「凡百の生徒」が、彼女に抱いていた「勝手なイメージ」が、ぽろぽろと脆く剥がれていくようにも見えた。
清々那 帰莢は、それまで、「ちょいすごいただの人間」ぐらいに、周囲の者たちからも思われていた。
養父が「瞳術の復興者」であり、さらに過激な魔人排斥活動を行うメンバーの一員であるという肩書から、彼女の行動の一切の理由は、そこに起因すると思われていた。彼女の異常な回避能力も、瞳術使いである養父から、直々に教わったものであり、決して「人間の域」を出ないと思われていた。
自分と同じただの人間である、そんな一般生徒たちの幻想は、あまりにも過激な形で、手酷く裏切られた。「よく分からない、クールでミステリアスな存在」は、「何を考えているか分からない不気味な生き物」となり、周囲の一般生徒たちの羨望は、拒絶へとスライドし、より強い負の感情を交えて彼女は見られるようになった。
その結果、彼女のそれまでの「功績」は、さしずめ「狂気」によるものとして、風紀委員会の中でも認知された。
風紀委員の大半が、清々那 帰莢はそういうものだと割り切る中、黒姫 射遠は、持ち前の正義感とそこから来る面倒見の良さ、そして自身の生い立ちから、彼女を割り切ることができずにいた。それは彼女の優しさでもあり、彼女が女子生徒からも人気となる要因のひとつであった。
しかし、だからといって、黒姫 射遠は彼女を認めることも、同じような理由からできなかった。その一件以来、清々那 帰莢の影は、常に黒姫 射遠の視界から離れることはなく、現場に駆け付けた彼女をいつも苛立たせた。
それ故、その矛盾が、黒姫 射遠に遠回しな態度をとらせてしまうのも、仕方の無いことである。彼女自身、自分の感情が「心配」であるということに気づいていないのだから。
その知らせも、黒姫 射遠が風紀委員同士の連絡のために使っている携帯電話へではない、あくまで私的に使っているものへ、その報は入った。
学園全体に暴動が広がったのが、その十分後である。
黒姫 射遠を筆頭に風紀委員会が戻ってきたとき、一部の生徒が引き起こしたこととはいえ、そこは休戦協定が結ばれる前の、ハルマゲドン真っ只中の学園を彷彿とさせずにはいられないほど、学園は荒んでいた。
番長グループと、生徒会も駆けつけ、暴動はものの十分で鎮圧されたが、生徒たちの間に生じた「亀裂」は、致命的であった。
事はすぐに鎮圧されたとは言え、風紀委員が、手薄となった学園をまかされており、学園内には風紀委員の人間が残っていた。そのうち一名は、その光景を終始見ていただけという話だ。これを未然に防ごうとせず、さらには事態を看過していたことは重大であり、風紀委員会の責任問題となった。その結果、風紀委員会は、その発言権は急速に縮小させられた。
黒姫 射遠は、清々那 帰莢を恨んだ。そして、彼女を信頼した自分が情けなく、悔しかった。
だが、そのような惨劇のただ中にいて、清々那 帰莢も決して無事ということはなかった。彼女は、普通の人間はもちろん、魔人ですら、死んでいても可笑しくないような深手を負いながら、事の勃発から鎮圧までを、平然と突っ立ったままであったと言う。
殺しかねない勢いで、手当を受けていた清々那 帰莢のいる保健室の扉を叩いた黒姫 射遠でさえ、彼女の傷を見て、その怒りが引いてしまうほど、彼女の負傷は常軌を逸していた。
それは間違いなくただの人間にとって死傷と成り得るものであった。
頭皮はぱっくりと裂け、頭蓋骨の中身が垣間見える頭部。半分閉じられた瞼から、流れ落ちる赤黒い血の塊。そして、体の半分にも至る火傷。目につくものだけでも、その一つ一つが間違いなく重傷に違いがなかった。
そのくらいじゃ人間は死なない。そう言うのは簡単だが、実際にその姿を見たものにとって、その姿は、"生き物"ではなく、単なるグロテスクなオブジェクトであって欲しいと、そう願わずにはいられないほど、その姿は筆舌し難いものであった。
黒姫 射遠など、それなりの能力を持った魔人なら、それで彼女についてある程度合点はいく。だが、「凡百の生徒」は、その傷が日を増すごとにみるみると、跡形もなく再生していくのに、言葉にできない恐怖を、感じてしまっていた。
それは、「凡百の生徒」が、彼女に抱いていた「勝手なイメージ」が、ぽろぽろと脆く剥がれていくようにも見えた。
清々那 帰莢は、それまで、「ちょいすごいただの人間」ぐらいに、周囲の者たちからも思われていた。
養父が「瞳術の復興者」であり、さらに過激な魔人排斥活動を行うメンバーの一員であるという肩書から、彼女の行動の一切の理由は、そこに起因すると思われていた。彼女の異常な回避能力も、瞳術使いである養父から、直々に教わったものであり、決して「人間の域」を出ないと思われていた。
自分と同じただの人間である、そんな一般生徒たちの幻想は、あまりにも過激な形で、手酷く裏切られた。「よく分からない、クールでミステリアスな存在」は、「何を考えているか分からない不気味な生き物」となり、周囲の一般生徒たちの羨望は、拒絶へとスライドし、より強い負の感情を交えて彼女は見られるようになった。
その結果、彼女のそれまでの「功績」は、さしずめ「狂気」によるものとして、風紀委員会の中でも認知された。
風紀委員の大半が、清々那 帰莢はそういうものだと割り切る中、黒姫 射遠は、持ち前の正義感とそこから来る面倒見の良さ、そして自身の生い立ちから、彼女を割り切ることができずにいた。それは彼女の優しさでもあり、彼女が女子生徒からも人気となる要因のひとつであった。
しかし、だからといって、黒姫 射遠は彼女を認めることも、同じような理由からできなかった。その一件以来、清々那 帰莢の影は、常に黒姫 射遠の視界から離れることはなく、現場に駆け付けた彼女をいつも苛立たせた。
それ故、その矛盾が、黒姫 射遠に遠回しな態度をとらせてしまうのも、仕方の無いことである。彼女自身、自分の感情が「心配」であるということに気づいていないのだから。
■■■■■
清々那 帰莢は黙っていた。言葉を選ぶようにして、二、三度口を開きかけたが、首を振りそのまま、口を噤んでいた。
その態度が、黒姫 射遠をさらに苛立たせた。
「風紀委員会の仕事にやる気がないなら、辞めてもらってもいいのよ?」
黒姫 射遠は、半分は本気で、しかし脅しのつもりで、彼女に告げる。
あの一件以来、学園内の争いは頻発している。そのせいで、現場に駆け付けるのが、遅れてしまうことが多々あった。清々那 帰莢がいくら死ににくいとはいえ、たった独りで、相手の攻撃を避け続けることはできない。相手が複数なら尚更だ。そのためか、彼女もダメージを受けることも多くなった。今は、それほどではないが、今の調子でダメージを受け続ければ、そのうち本当に死んでしまうかもしれない。
しかも、彼女の場合、彼女が「瞳術使い」であるという事が、「ただ見ているだけ」の彼女の行動に意味を持たせた。噂には尾ひれがつき、さまざまな憶測を生んでいた。
黒姫 射遠は、清々那 帰莢を案じていた。もし、彼女が風紀委員としてやっていくつもりがないなら、それも構わない。その方が、彼女のためだと言う考えもあった。
このままでは、自分の体が持たないことも、理解しているだろうと、黒姫 射遠は考えていた。しかし、清々那 帰莢は、一切考える素振りもなく即答した。
「辞めません」
それは、頑なな拒絶だった。どうして、そのようなことを言うのか、そう言いたげに清々那 帰莢は、黒姫 射遠の眼を見据えた。
この態度は、黒姫 射遠にとって、少し予想外であった。普段から、無愛想で、表情すらまともに作ろうとしない彼女が、明らかに敵意を向けて、自身を見つめていた。
黒姫 射遠は、こんな表情もするのか、と内心驚いていた。
「け、けどね」
黒姫 射遠は、それに面食らいながらも、落ち着きを取り戻そうとする。しかし、清々那 帰莢は続けた。
「あなたは、どうして、いつもいつも、わたしに干渉するの?」
清々那 帰莢は、苛立たしげに語調を強めた。
「そ、そんなの――」
黒姫 射遠は、一瞬言葉にどもる。そして、絞り出すように、
「風紀委員として当たり前のことでしょ!」
と、清々那 帰莢に言い放った。それを聞き、先ほどからくすくす笑っていた汚水ぎゃんが、とうとう堪え切れなくなったのか、けらけらと笑いだした。
「そこ、うるさい!」
黒姫 射遠が、声をあげる。他の委員たちが、怯む中、汚水ぎゃんは、『わかった、わかった』と手を挙げ、ひーひーと息をしながら、涙をぬぐう。
黒姫 射遠は、凛とした表情で、清々那 帰莢を睨み返す。
「あなたがそのつもりなら、もう私が持ってきたものだって、食べたりしないでね!」
汚水ぎゃんが、盛大に噴き出す。とばっちりが来るのではないかと、はらはらする周りのことなど、お構いない。
黒姫 射遠も、それが、的外れであるというのも、分かっていた。清々那 帰莢も、彼女が本気でそう言っているのではなく、一種の衝動からそんな発言をしてしまったというのを、分かっていた。
しかし、清々那 帰莢も大概ではなかった。
「ケーキなら、自分で作れます」
ぷつんと、何かが切れるような音が、その瞬間、聞こえたような気がした。
黒姫 射遠は、
「あ゛ー! もういい。あなたなんか知らないんだから!」
そう言ってどかどかと部屋を跡にした。
「姫ちゃん!」
「姫!」
その後を何人かが連なっていく。
黒姫 射遠がいなくなると、その一室には、汚水ぎゃんと清々那 帰莢だけが、最後には残っていた。
「クスクス……いやぁ、おまえ最高だぜ。姫のあんな顔が拝めるなんてな」
汚水ぎゃんは、楽しそうにマンホールを手で回していた。
清々那 帰莢は、そんな汚水ぎゃんを無視して、窓際に寄ると、ぼそっと小さく呟く。
「ケーキ、もう食べれないんだ……」
少し、その表情は寂しげであった。
その態度が、黒姫 射遠をさらに苛立たせた。
「風紀委員会の仕事にやる気がないなら、辞めてもらってもいいのよ?」
黒姫 射遠は、半分は本気で、しかし脅しのつもりで、彼女に告げる。
あの一件以来、学園内の争いは頻発している。そのせいで、現場に駆け付けるのが、遅れてしまうことが多々あった。清々那 帰莢がいくら死ににくいとはいえ、たった独りで、相手の攻撃を避け続けることはできない。相手が複数なら尚更だ。そのためか、彼女もダメージを受けることも多くなった。今は、それほどではないが、今の調子でダメージを受け続ければ、そのうち本当に死んでしまうかもしれない。
しかも、彼女の場合、彼女が「瞳術使い」であるという事が、「ただ見ているだけ」の彼女の行動に意味を持たせた。噂には尾ひれがつき、さまざまな憶測を生んでいた。
黒姫 射遠は、清々那 帰莢を案じていた。もし、彼女が風紀委員としてやっていくつもりがないなら、それも構わない。その方が、彼女のためだと言う考えもあった。
このままでは、自分の体が持たないことも、理解しているだろうと、黒姫 射遠は考えていた。しかし、清々那 帰莢は、一切考える素振りもなく即答した。
「辞めません」
それは、頑なな拒絶だった。どうして、そのようなことを言うのか、そう言いたげに清々那 帰莢は、黒姫 射遠の眼を見据えた。
この態度は、黒姫 射遠にとって、少し予想外であった。普段から、無愛想で、表情すらまともに作ろうとしない彼女が、明らかに敵意を向けて、自身を見つめていた。
黒姫 射遠は、こんな表情もするのか、と内心驚いていた。
「け、けどね」
黒姫 射遠は、それに面食らいながらも、落ち着きを取り戻そうとする。しかし、清々那 帰莢は続けた。
「あなたは、どうして、いつもいつも、わたしに干渉するの?」
清々那 帰莢は、苛立たしげに語調を強めた。
「そ、そんなの――」
黒姫 射遠は、一瞬言葉にどもる。そして、絞り出すように、
「風紀委員として当たり前のことでしょ!」
と、清々那 帰莢に言い放った。それを聞き、先ほどからくすくす笑っていた汚水ぎゃんが、とうとう堪え切れなくなったのか、けらけらと笑いだした。
「そこ、うるさい!」
黒姫 射遠が、声をあげる。他の委員たちが、怯む中、汚水ぎゃんは、『わかった、わかった』と手を挙げ、ひーひーと息をしながら、涙をぬぐう。
黒姫 射遠は、凛とした表情で、清々那 帰莢を睨み返す。
「あなたがそのつもりなら、もう私が持ってきたものだって、食べたりしないでね!」
汚水ぎゃんが、盛大に噴き出す。とばっちりが来るのではないかと、はらはらする周りのことなど、お構いない。
黒姫 射遠も、それが、的外れであるというのも、分かっていた。清々那 帰莢も、彼女が本気でそう言っているのではなく、一種の衝動からそんな発言をしてしまったというのを、分かっていた。
しかし、清々那 帰莢も大概ではなかった。
「ケーキなら、自分で作れます」
ぷつんと、何かが切れるような音が、その瞬間、聞こえたような気がした。
黒姫 射遠は、
「あ゛ー! もういい。あなたなんか知らないんだから!」
そう言ってどかどかと部屋を跡にした。
「姫ちゃん!」
「姫!」
その後を何人かが連なっていく。
黒姫 射遠がいなくなると、その一室には、汚水ぎゃんと清々那 帰莢だけが、最後には残っていた。
「クスクス……いやぁ、おまえ最高だぜ。姫のあんな顔が拝めるなんてな」
汚水ぎゃんは、楽しそうにマンホールを手で回していた。
清々那 帰莢は、そんな汚水ぎゃんを無視して、窓際に寄ると、ぼそっと小さく呟く。
「ケーキ、もう食べれないんだ……」
少し、その表情は寂しげであった。