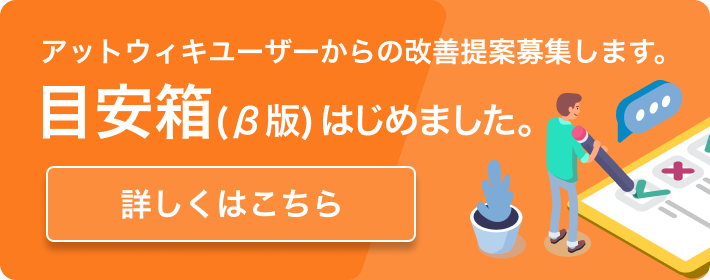ジョジョの奇妙な聖杯戦争
真なる英雄
最終更新:
匿名ユーザー
-
view
-
「たとえば、だ。アーチャーよ。君は何をもって死者の存在を実証する?」
壊れた屋根から落ちる雨が、朽ちた机を静かに濡らしていた。プッチは、一段高い教壇から、静かに話していた。
アーチャーは、壊れた机の上に寝そべっていた。
「それは洒落事か?・・・感傷的な言い方をするなら・・・思い出やら・・・記憶・・・記録と言った方がいいか?そういうものだろうな」
屋根も仕切りもない懺悔室では、ホワイトスネイクが自分が今まで収集した記憶を整理していた。
『歴史トハ、記憶ノ積ミ重ネ。繋ガル記憶。思イガ、人ノ歴史トナル』
「だが・・・それでは記憶に残らなかった人間は存在しない、というのかな?名無しの英霊よ」
「・・・・・・・・・・」
アーチャーは天を仰いで、目を瞑った。時折、腐敗した屋根板より、水滴が鼻先に滴り落ちる。
「私は名無しではない・・・・思い出せないだけだ」
「同じだよ。記憶が存在しなければ、墓場の下で眠っているのと同じだ。主なるイエス・キリストは人々に記憶されている。
そして聖杯、聖槍、聖骸布、彼の記録が、彼を現在まで生かしているのだ」
『カツテ、アル男ガイタ。彼ハコノDISCニ記憶トすたんどヲ封ジ込メラレ、刑務所デ生者デモ死人デモナイ人生ヲ続ケテイル』
ホワイトスネイクはゆっくりと立ち上がり、音も立てずにアーチャーの元に歩み寄る。
「何が言いたい。ロベルト・プッチ。いや・・・エンリコ・プッチよ?」
いささか皮肉混じりの口調で、アーチャーはプッチに言った。
「なあに・・・君を蘇らせたいだけだ・・・忘却より、な」
次の瞬間、ホワイトスネイクの腕が、アーチャーの頭中に入り込んでいた。
- 「どうだ?ホワイトスネイクよ」
『マダナントモ言エナイ。英霊ノ精神構造ハ普通ノ人間ト違ウ。英雄ハ短命ダガ・・・英霊ノ記憶ハ長イカラナ』
ズブズブと音を立てて、ホワイトスネイクの腕が沈み込む。アーチャーは、濁った目で空を見つめるばかりで、一切の反応がない。
『・・・見ツケタ。記憶ノ隙間ニデキタ絶対ノ領域ニ隠レテイタ。間違イナイ。コレガアーチャーノ封印シタ記憶ダ』
「封印・・・そこまでして忘却の彼方に捨て去りたかった記憶だったのか・・・?」
『ばらばらダ・・・ダガ、記憶ハ本来形ヲ持タナイ。復元ハ可能ダ』
「よし、サルベージしろ」
「・・・・・は!・・・エンリコ・プッチ!何をした!」
さっき横たわっていた場所の上にアーチャーはそのまま寝ていたが、頭には、痛感とも違う、不愉快な感触がしていた。
「・・・・君の記憶を復元させてもらった。失礼な行為であったことは、謝ろう」
「・・・・どんな記憶だ?」
「君がここに来る以前の記憶・・・私が確認した方が良かったかな?」
咄嗟に、アーチャーはプッチの手にあった、DISCをもぎ取った。
「いらんことをするな!自分の過去は自分で清算する・・・だが、手間が省けた。その点は感謝しよう」
「・・・使い方は分かるな?」
「ああ。頭部に差し込めばいいんだろう?」
アーチャーは、そのDISCを静かに眺めた。薄らと、歯車と剣の姿が見える。だが、遠くの風景を眺める青年の姿も見える。
何も見えるが、何も見えない。不明確な記憶そのものだ。
「・・・・・・・よく帰ってきたな。我が記憶よ」
そして、ゆっくりとそのDISCを自分に頭部に押し当てた。やがて、ゆっくりとDISCが脳髄のさらに奥の、名状しがたい部分に分け入っていく。
- 「・・・・・・・・・バカな」
DISCが完全にアーチャーの頭脳に固着した瞬間、アーチャーが静かなうめき声を上げた。
『時ニ、目覚メルベキデナイ記憶トイウモノガアル・・・アーチャー・・・君モソレカナ?』
「アーチャーよ。君は一体何を思い出した?」
「・・・・・・泥・・・・・標・・・・の・・・・・帝・・・・神・・・・・園・・・・バカ・・・・な」
アーチャーの唇は、微かに震えていた。
「どうした?アーチャーよ」
プッチ神父は、アーチャーに手を差し出した。と、突然アーチャーはその手を払いのけた。
「ええい!私に触るな!」
「・・・・・・!?」
「違う・・・違う!私は・・・・違う!・・・・私は・・私は・・・こんなものに!」
アーチャーは、頭を抱えて、激しく身悶えしていた。と、突如アーチャーは机に置かれていたDISCを掴み、それを押し込んだ。
「! 何をする!アーチャー!」
だが、アーチャーはその静止も聞かずに、そのDISCを自分の頭に挿入していた。
「記憶!違う!エンリコ・プッチ!違う!マスター!俺は!」
次の瞬間、アーチャーは教会の巨大な扉に向けて走っていた。そして、そのまま戸外に出ていた。
「違う・・・・・・・・この世界は!・・・・・ジョニィジョースター・・・・・そうか!・・・そうだったのか・・・!」
雨が降りしきる中、赤い服を着た男の姿は、静かに消えていった。 -
先に丸い綿が付いた棒を使って、小次郎は吉良邸の門の下で、静かに刀の手入れを行っていた。
「近頃は便利な時世になりもうしたなあ。このベビーパウダーとやらは、刀の手入れにちょうどいい」
『キャスターも機嫌がよさそうにしていたしなあ』
「何故でござるか?」
キョトンとした表情で、小次郎はアヌビスに聞き返した。
『お前に頼まれて薬局に行った時は機嫌悪そうにしていただろう?だがなあ、店員が聞いたそうだ。赤ちゃんに使うんですか?ってな。
そんなことは絶・・・・・・・対にないのになあ?』
小次郎は、大声を上げて呵呵大笑した。
「はっはっは、それもそうでござるなあ」
爆発。
「あいたた・・・・どうやらこの雨でも、聞こえているようでござる」
『うむ・・・・・気をつけよう』
腰を抑えながら、小次郎は立ち上がった。と、外を見た瞬間、顔が綻んだ。
「見られい、アヌビス。雲が晴れていくぞ。おう・・・虹が」
『・・・・・幽霊になっても、こういう景色を見るのはたまらんなあ』
「全くでござる・・・・・・・・・」
ゆっくりと雲が切れ、綿菓子のように雲散していくと、そこから日光が差し込み、やがて、鮮やかな七色の橋を作った。
「うむ、絶景かな、絶景かな、値千金」
腰を真っ直ぐにして、小次郎はその虹を眺めた。
『さて、小次郎、晴れたことだし・・・・』
その時、カラン、と何か金物が落ちる音がした。三本分の音がした。
『小次郎?』
だが、反応はなかった。
『おい、小次郎、小次郎?小次郎?小次郎!?』
だが、そこには三本の刀しかなかった。
- 「ホリイ!?どうしたのですか!?ホリイ!?」
セイバーは、洗濯物を干そうと縁側を出た瞬間、突如倒れたホリイを抱きとめた。しかし、一寸の反応もなかった。
「ホリィ!?ホリイ!?ホリイ!?」
目を痛めるほどに綺麗な虹が、今にも手でつかめそうなところにかかっていた。
「ヤバイ!スタープラチナ!」
承太郎は、咄嗟の判断で動いていた。外に出た瞬間、ホリイは倒れた。少なくとも、屋内の方が安全だ。
時を止め、セイバーとホリイは抱えると、家の中に飛び込んでいた。
「く・・・・・なんだ、一体!?・・・・・・これは!?」
ホリイは、ぐったりとしていた。死んではいない、生来の波紋の、ほぼカンでしかない感覚で分かる。だが―その手は―。
「く・・・あ・・・・ホリイ!?大丈夫ですか・・・あ、痛ッ・・・・・」
咄嗟にセイバーは指を抑えた。切れてはいなかったが、何か鋭利なものに触れてしまったようだった。
「・・・・・・・・剣・・・・・?これは!」
セイバーと承太郎は、ホリイの手を見た。そして、絶句した。
剣になっていた。肘から先が完全に剣になっていた。
「これは・・・・・・・・・」
承太郎は、その剣に触れてみた。鋭利ではあるが、斬れる代物ではない。派手さはないが、質素に綺麗な装飾が施してある。
「敵の・・・・・・攻撃!?」
セイバーは、咄嗟にさっきホリイが立っていた場所を見た。そこには、綺麗な虹がかかっているだけだ。
「どうやら・・・・・そのようですね」
階段から、ジョニィを抱えてライダーが降りてきた。
-
二階では、ジョセフ様も同じような症状で窓際に倒れていました。既にベッドに寝かせてあります。それどころか、道路では完全に剣になってしまった人々が何十人も・・・・というか・・・貴方達も」
はっ、と承太郎とセイバーは自分の手を見た。ホリイほど侵食されてはいないが、指先が硬質化していた。うっすらと、平たく、鋭利になりつつある。
「敵の攻撃・・・ジョセフ様が倒れていた窓の視線の先にも、虹がかかっていました。間違いなく、虹からは魔術の構成が感じられました」
「いや、魔術だけじゃない」
畳の上で胡坐をかいているジョニィも、話し始めた。
「聖人の手の精霊が教えてくれた。というか、感じた。あの虹には、スタンドパワーの影響も感じられる。あれは、スタンドであり、魔術なんだ」
「虹・・・か。つまり、お袋はあの虹を見ちまったから、こうなったってわけか。じゃあ、ジョニィ。どうしてお前には何の影響もない?」
ジョニィは、自分の右手を眺めた。
「・・・前も、敵のスタンド攻撃を受けたことがある。スケアリーモンスターズ、だったかな。あの攻撃も、聖人の遺体が中和してくれた。恐らく、それと同じ影響だろう」
「私は、視覚を封印しています。ですから、あの虹を『見て』はいません。おそらく、視覚に訴えかける攻撃なのでしょう」
「そうですか・・・」
しばし、沈黙が居間を覆った。その沈黙を、承太郎の言葉が破った。
「頼めるか?ジョニィ」
「ああ。任せてくれ。・・・俺はこの家の人達が好きだ。俺がこの現象を止める。行こう、ライダー」
「はい、ジョニィ」
ライダーは、ジョニィを抱えた。そして、居間に片付けてあった車椅子を取り出し、そこに乗せた。
「・・・・・・・ライダー」
「なんですか?セイバー」
「・・・・・・私も、ホリイが好きです。・・・・・頼みます」
「・・・・・ええ」
-
日傘をしまい、フードを脱いで、キャスターは門の下に落ちていた刀三本を吉良に渡した。一本はアヌビス。一本は小次郎愛用の刀。もう一本は見慣れない長い刀。
「・・・・間違いありません。小次郎の魔力の残滓を感じます。敵の・・・攻撃でしょうか?」
吉良は、黒いカーテンで閉じられた窓と、幾らか硬質化した自分の指を眺めて呟いた。
「攻撃・・かは分からないがね。分かるのは、異様な現象であることだけだ」
『分からん・・・晴れたと思ったら小次郎が消えていた。間違いなく、現象は晴れた瞬間に始まっていた。どうするのだ、吉良吉影』
「何もしない」
「え?」
キャスターが頓狂な声を上げた。
「既にこの現象は街一体に広がっているようだ。父さんが教えてくれた。街の人間の大半は剣になってしまったようだ。だとしたら、他のマスターが動いているだろう。彼らが勝手に決着をつけてくれる。
それで現象が収まればそれでよし。収まらないなら、私達が漁夫の利を狙えばいい」
「・・・・分かりました。念のため、一帯に結界を貼っておきます。吉良様、くれぐれもお気をつけて・・・」
吉良は、キャスターがドアから出て行ったことを確認すると、ゆっくりと椅子から立ち上がった。そして、モダンな蓄音機のデザインのCDプレイヤーに、モーツァルトのCDを入れた。
しばし、どこまでも澄み切った音楽に、吉良は身を任せてロッキングチェアに座っていた。そして、ふと、無機物が静かに眠る世界のことを思った。
―それはそれで、一つの楽園の形態じゃないか―
そして、ゆっくりと目を閉じた。
-
車椅子にはしっかりと油がさしてあったので、かすれた音は少しも出なかった。
「・・・・しかし、人間が剣になるなんて、一体どういう攻撃なんだ?」
「そのことですが、ジョニィ」
「ん?」
ライダーは、道端に落ちている剣も車輪で踏みつけながら、うだるような陽光下をズンズン進んでいった。道には、さっきの豪雨の影響で、大量の水溜りができていた。
「おおよその敵の姿は分かりました」
「何?」
「この虹は、二つの能力で構成されています。一つは『人間の原始的な本能に訴えかけ、その姿を変えてしまう力』・・・・だと思います。スタンドは専門外なので、はっきりとは言えませんが。
もう一つは・・・・虹を構成するプリズムが、魔力の視覚をとおして見ると分かるのですが、微小な呪文で構成されているのです」
「呪文?何のだい?」
しばし口を噤んだ後、ライダーは呟いた。
「‘I amboneofmysword.‘・・・・こんな個性的な魔術構成を編めるのは一人しかいません。・・・・無限の剣製・・・アーチャー」
「アーチャー・・・・白髪の男か。彼がホワイトスネイクとかいうスタンドからDISCを与えられた・・と考えるのが妥当だな・・・ん」
「どうしました?」
ジョニィが、前方を指差した。
「あの水溜り・・・・・・・動かなかったか?」
「え?気のせい・・・・・!すみません、ジョニィ!」
次の瞬間、ライダーが思いっきりジョニィの車椅子を横に突き飛ばした。水溜りから醜悪な手が伸び、ライダーの皮膚を切り裂いたのと同時だった。
- 「くうう・・なんだ!今のは!?」
ジョニィは、体を起こしてライダーを見た。ライダーの肩は、深く切れており、そこから鮮血が滴り落ちていた。さっき手が伸びていた水溜りには、うっすらと波紋が残っているばかりだった。
「間違いなく・・・攻撃!」
「く・・・・・水を使ったスタンドか!?」
「・・・・・・・・二人、剣になった。更に一人。目標攻撃に失敗、か・・・難しいな。車椅子が倒れた。起き上がったか。使い魔がかばったようだな。
水滴音・・・・・・出血量、高度からして、肩が切れた切り口は4cm・・・・5cm・・・4,7cmか・・・・まあいい」
森の奥、そこに一人の男が座っていた。彼は、ぶつぶつと何事か呟いていた。
「・・・・・あのお方の運命か・・・・・あと何回だろうか・・・・・・だが時間は近い・・・我らの・・・よ」
彼の足元の水溜りが、かすかに動いた。
「・・・敵は今、水面から攻撃をしてきた!順当に考えれば・・水のスタンド!ライダー!」
「分かっています・・・・・・・・血が・・・しかし!」
ライダーは、傷口に指を当てた。ぶしゅ、とさらに鮮血が吹き出る。
「しかし・・・・丁度いいですわね」
ライダーは、自分の赤黒い血液を、舌先で、淫靡な動きで、ねっとりとした舌使いで舐めとった。
もう一度、ライダーの足元の水溜りが動き始めた。そこから、鍵爪がついた手が伸び始める。
「この現象の犯人の手下かしら・・・・?どっちでもいいですわ。ただ、倒します!」
「ライダー!」
ライダーは、傷口から染み出した血を、地面に垂らした。その血が、静かに規則的な模様の円陣を描く。
「・・・・・・ジョニィ、この事件の犯人は貴方に任せます!私はこの敵を!」
次の瞬間、魔方陣が光り、激しい閃光が飛び散った。 -
閃光が止んだ瞬間、その魔方陣の上には、一匹の馬がいた。いや、馬と呼ぶべきか、それはまさに、伝説の聖獣、ペガサス。
と、ライダーは突然腰からナイフを取り出し、ペガサスの目を切り裂いた。
「許しなさい!」
ライダーの忠実な足であるペガサスは、一瞬荒い鼻息を漏らしたが、微動だにしなかった。
「な・・・・・・・・何をしているんだライダー!目潰しはともかく、理由を言えぇぇぇぇぇ!」
「・・・剣の虹を防ぐにはこれしかなかった。しかしジョニィ。貴方の技能と聖人の腕の神性なら、ペガサスを扱える。貴方なら、ペガサスの眼になれる!行ってください!」
ジョニィは、ゆっくりと『タスク』を回転させた。そして、一気に上半身のバネで地面を叩く。
ゆっくりと空中を跳躍しながら、ジョニィは言った。
「・・・・・・君の思い、よく分かった!君の愛馬、僕の足として、使わせてもらう!」
一気に、ジョニィはペガサスの鞍に乗った。ベルラフォーンを握り、ジョニィは叫ぶ。
「ハアッ!神話の時代から生きる誉れ高き名馬よ!僕の息遣いが分かるな!?僕の足になって、飛べ!僕が君の目だ!」
ペガサスの翼が、展開する。次の瞬間には、ペガサスは天に舞い上がっていた。
「任せたぞ、ライダー!」
「そちらこそ!ジョニィ!」
光の尾を纏いながら、ペガサスは天に消えていった。ライダーはそれを見送ると、再びナイフを構えた。
水溜りからは、醜悪な手が、ゆっくりとのび始めていた。
「・・・・・・・・・見せてあげましょう。英雄の戦いを」
-
「・・・・・・・・風?・・・・飛んだか・・・・話には聞いていた・・・天馬か・・・
敵は一人・・・・・体格・・体重・・・女か・・・・距離5400・・・・斬れ!・・・・外した。ナイフで防いだな。
・・・・・・走り出した?・・・ゲブ神、補足、その水溜りに移れ・・・なに?・・・早すぎる・・・・・・
・・・なんだ?・・・この動きは何だ!?・・・・走っていない・・・歩いてもいない・・・分からない・・こんな動きをする人間は・・・
3000だと!?早すぎる・・・・そこだ!・・・2300!?・・・・・1700!?なんだこの動きは!?
駄目だ・・・動きが読めん・・・ゲブ神、1000で待つんだ・・・この動き・・・聞き覚えがある・・・三つの時か・・・
・・・・・・コブラの這う動き・・・・・・・・・・・補足したな!一気に切り裂け!・・・・素通りしただと!?なぜそんな芸当ができる!?
駄目だ・・・俺の聴覚でも補足しきれないとは・・・く・・・やめろ・・・これ以上剣を作るな!・・・400・・・・200・・・
50・・・・・・・・・・0」
ンドゥールは、手から杖を取り落とした。もう、必要がなくなったからだ。ライダーは、彼の真後ろの立っていた。
「・・・・・・見事だ。まるでコブラのように、しなやかな動きで俺の結界を潜り抜けるとはな。・・・これが英雄の力か」
「・・・・・・・見事と言うべきは私の方ですね。負けたとはいえ、この剣の虹が始まったタイミングで攻撃を仕掛けるとは。しかも・・・・貴方、盲人ですね」
ンドゥールは、微かに唇を持ち上げ、声を上げずに笑った。
「ふふ・・・・・・・それは違うぞ。二つ、お前は間違っている」
「? なにが?」
「一つは・・・・・・俺がこのタイミングを狙って攻撃を仕掛けた、ということだ」
「え?」
「もう一つは・・・・・・俺の敗北だ!」
ンドゥールは、標的の真後ろからゲブ神の腕を伸ばした。この距離、見えていようが見えていなかろうが、なにも問題ない。
「我が主の為・・・・死ね!」
次の瞬間、確かにライダーを切り裂いた感触を、ンドゥールは感じた。
-
「はあ・・・はあ・・・はあ・・・・危なかった・・・・あと一秒遅かったら、俺の負けだった・・・」
足元に、血溜まりが広がる感触が、確かに広がっていた。
「ふふ・・・結界を突破された時は冷や冷やしたが・・・・・私の勝ちだ・・・・・・英雄よ・・・はは・・・?・・・」
その瞬間、ライダーの死体の反応が消えた。
「・・・・なに?」
次の瞬間、ンドゥールの漆黒の視界に、一人の反応が現れた。
「避けたのか!?ゲブ神!」
再びゲブ神が反応を切り裂いた。だが、反応は再び現れた。
「バカな!?本物のバケモノか!?クソ!クソ!クソ!」
だが、斬っても斬っても、ンドゥールの感覚には、新しい反応が現れるばかりだった。
「まだ分かりませんか?」
突如、ライダーの声がした。
「貴方は既に私の結界の中に入っているのです。ブラッドフォート・アンドロメダの中に」
はっ、とンドゥールは自分の右手に左手で触った。両の手は、グニャリ、と音を立てそうな勢いで、異様な方向に折れ曲がった。
「溶解・・・・・・・・・の力か」
「貴方に残された自由は二つ。しかし、行き先は一つ。どちらを選びますか?」
- 「・・・・・・・・・・・」
ンドゥールは何も言わなかった。そして、ゆっくりと自分の頭部にゲブ神を生やし、自分の頭を貫いた。
「ふ・・・・・・・これでいい・・・・・・これも運命だ・・・・昔から知っていた・・・恐ろしくはない・・・」
ンドゥールの呼吸音は、すでにゆっくりとした速度になり始めていた。そのンドゥールに、ライダーは尋ねた。
「・・・答えなさい。さっき言っていたことはどういうことですか?」
「・・・・・・・・・なんのことだ?」
「とぼけないでください。貴方がこのタイミングで攻撃を仕掛けてきたのはどういうことですか?それともアーチャーの仲間なのですか?」
「俺は・・・そのアーチャーという男の仲間ではない・・・ただ、行動を起こさなければならなかっただけだ・・・・ところで・・お前は、感じないのか?」
「?」
「・・・・・辻褄が合わないと思わないか?」
「何がですか?」
「・・・・・・・・・・何故、お前は戦い続けるのだ?」
「私の戦う理由を聞いているのですか?」
「違う・・・・・・そうでは・・・・・・ない」
「・・・・・・・・??」
「何故・・・・・・・・この世界は・・・・・なない・・・・のだ・・・?・・・・この俺も・・・・・何故・・・?」
「貴方、一体何を言っているのですか!?」
「・・・・・・・・・・・俺は・・・・・・・・・繰り返す・・・・・・それは・・・・・・我が・・・・・・・・英雄」
「英雄!?何を言いたいのですか!?貴方!?答えなさい!」
しかし、答えは永遠に返ってくることはなかった。
- 「なんてことだ・・・・・・」
空から町を眺めて、ジョニィは愕然とした。町の住民は、完全に沈黙していた。
さっき、盲目の老人と目がつぶれた猫が道を横切っただけで、全ての生命が剣と化していた。
「これは・・・・・のんびりもしていられないな。行くぞ!ペガサス!」
ジョニィは、ペガサスを旋回させた。
「くそ・・・・何故だ・・・・・・・この世界は・・・・・・俺は・・・・しかし・・・奴を・・・葬らなければ」
ふらふらと覚束ない足取りで、アーチャーは静かな世界を歩いていた。外気はさっきの土砂降りのせいで、陽炎を作り出していた。
「だが・・・・まだ・・・間に合うのか・・・・だとすれば・・・・・早く・・・・・・」
陽炎の中、亡霊のようにアーチャーは歩いていた。アーチャーが歩くたびに、金属の落下音が響く。
「くそ・・・くそ!どうしてこうなるんだ!・・・俺は・・・俺は!」
陽炎は、アーチャーを亡霊のように路上に浮かび上がらせる。
「だが・・・・何故だ・・・・・・あの時・・・・・壊れたはずなのに・・・」
その時だった。空気を切り裂く音が一帯を駆け抜ける。
「・・・・・・何故このタイミングで来る・・・・・・何故だ!」
「・・・・・見えた!ペガサス、僕の息遣いが分かるな!このまま距離を取れ!・・・よし、いけ!タスク!」
ジョニィは、爪を回転させ『牙』へと変えた。そのまま回転する弾丸が、アーチャーへ向かって滑空していく。
アーチャーは、その攻撃に対して、避けることすらしなかった。
「トレース・・・・・・オン」
命中、そうジョニィは確信した。だが、アーチャーの顔に触れるか触れないかの寸前で、突如タスクが動きを止めた。
「何!?」
ジョニィは、空中で停止したタスクを見た。五発のタスクは、全て五本の、指程の大きさもない剣に貫かれ動きを止められていた。
それが、空気中の微生物を剣に変えたものだとジョニィが気が付くのは、後の話であった。
「無駄だ・・・今の私は・・・自分でも自分を抑えきれない・・・・時間はかからない・・・退け」
だが、ジョニィはペガサスの上から返した。
「どうして退ける?僕は承太郎と約束した!君は必ず撃つ!」
再び、ジョニィは再生したタスクを撃ち出した。
「無駄だと・・・・・・・言っているだろう」
再び微細な剣が出現した。確実にタスクを穿つ。
「・・・・・・どうしても来るか。ならば、いい」
再び虹が、天にかかる。
「今度は、避けられると思うな・・・・・・・・・」
アーチャーの瞳孔が、瞬間開いた。
- 「・・・・・・どこだ?どこから来る!」
ジョニィは手綱を操って、ペガサスに思い切りビルの壁を蹴らさせ、急静止をかけた。ビルの壁面が瓦解する。
「・・・・・・・・・・・・・・?」
キンと、金属音がした。
「・・・・・・・・!上か!」
ジョニィは天を見上げた。そして、絶句した。あえてその情景を描写するなら、もしも雲を構成する分子がFeだったら、と思わせる光景だった。
一斉に、数百本の剣が降り注いだ。
「上空の微生物を剣に変えたのか・・・・・・・・っと、そんな場合じゃない!」
ジョニィはペガサスを急降下させた。そして、着地に成功すると、即座に辺りを見回す。
「どこだ!どこに隠れればいい!?・・・・・あそこのショーウィンドウ!って、うあああああああ!」
微細な剣がジョニィの頬と足と顔と、ヤスリでこするように削っていく。だが、ペガサスも跳躍していた。
次の瞬間、ジョニィの体はブティックの中に放り込まれ、さらにガラス片で体を傷つけられていく。
「くううううううううう!・・・だが、凌ぎきれたか・・・・・っと、あ!?」
薄暗い店内、その端で、一人の女性がすすり泣いていた。ジョニィは、ペガサスをそこまで歩かせる。
「・・・・・大丈夫か!?君」
その女性は、褐色の肌をした、中々の美女だった。彼女はジョニィが手を差し伸べると、即座にジョニィに抱きついた。
「ああ・・・良かった!」
「え、ちょっと、君!?やめるんだ!」
女性は、心から嬉しそうな声でジョニィに言った。
「いえ・・・・いいの・・・・・・だって。
これで貴方に触れることができるから」
その瞬間、ジョニィの体を電撃が走った。 - 「ぐう!?なに?」
「・・・・・・・触ってはいけないものでも、人は触れてしまうものなのね。悲しいわ」
ジョニィはペガサスから落馬し、地面を転がった。ペガサスが、それを鼻先で追う。
「く・・・・くそ、敵かよ・・・・このブティックに隠れていたか・・・・ん?」
ジョニィは、自分の肩を見た。そこには、ダイヤが埋め込まれたネックレスが張り付いていた。
「ん・・・・・?外れない・・・・?」
ジョニィは、そのネックレスを体から離した。しかし、すぐにまた張り付いてくる。
「・・・・・・・・・・・・・これは・・・・磁石?・・・・・!」
店外から、ジョニィの体から発生した磁力に引かれて、数百本の剣が飛んできた。
ジョニィがそれに気がついた時には、ジョニィは回転の力で跳躍していた。そして、ペガサスの鞍にまたがり、ペガサスを駆け出させる。
「走れ!まっすぐだ!壁を突破したら上に飛べ!」
ペガサスは、ジョニィの呼吸に合わせ、突進した。魔力を使うまでもなく、その脚力で鉄筋コンクリートの壁を叩き壊す。
「上だ!視力がなくてもお前には僕の息遣いが分かるだろう!?最大加速だ!」
ペガサスは天を目掛けて飛び出した。
「これで・・・・・・・何!?」
剣は、いささかもその速度を緩めず、ジョニィ目掛けて飛んでいた。その剣の群れに呼応するかのように、剣がその数を増す。
「ふふ・・・・・」
陽光が届かないブティックの更衣室の中で、マライアはタバコの火を点けた。
「私のスタンド、バステト女神の力は、触れたものを全て磁石にする・・・さて、あと数十分、もつかしら?貴方が逃げ延びるのが先か、時間が来るのが先か・・・」
マライアは、たっぷりと紫煙を口から吐き出した。
-
「タスクで撃ち落すか・・・・・いや、あれだって人間なんだ!」
ペガサスは、既に地面の建物も見えない高度に達していた。それでも、剣の群れはいささかも減速していなかった。
「くそ・・・・このままじゃペガサスの体力がなくなるのが先・・・一か八かだ!合図で一気に急降下しろ!」
ペガサスは、荒い鼻息を吐き出すと、ジョニィの言葉に答えるように頷いた。
「・・・・・・よし、急旋回、急降下だ!」
ジョニィが手綱を叩くと、ペガサスは大きく旋回し、そのまま真下へと急降下した。
「うあああああああ!!」
最高速とはいえ、無事ではすまない。剣の群れとすれ違う瞬間、ジョニィとペガサスの全身に、確実に裂傷が増えていく。だが、それでも、それゆえ、ジョニィはさらに速度を上げた。
「まだだ!いいか!僕の呼吸で地面を蹴れ!そして、前に跳躍するんだ!」
果たして、地面が近づき始めた。剣も、ジョニィ目掛けて、急降下する隼のように距離を詰める。
この時のジョニィは、異常なまでに冷静であった。ジョニィは分かっていたからだ。ジョッキーは、いかなるときも恐れてはならないことを。
なぜなら、愛馬がもっとも恐れるのは、乗り手の恐怖だからだ。
「地面が見えた!よし、地面を蹴れ!」
ペガサスの豪脚が、地面を叩く。激しい閃光の尾を引きながら、一気に前方へと走っていく。
「よし!いいぞ!これでいい!僕達の勝ちだ!天馬よ!」
- 「ふー・・・・・・」
マライアは、もう一度タバコをくわえ、煙を吸い込んでいく。
「すでに最大磁力を与えたわ・・・・時間の問題ね」
そう思って、さっきジョニィが突っ込んできたショーウィンドウを眺めた。その時、マライアの目が見開かれた。
そのショーウィンドウから、再びジョニィとペガサスが突っ込んできたからだ。
「まさか・・・・・・こっちに体当たりをかけるつもり!?この・・・ビチクソがぁぁぁぁぁ!」
マライアの予想通り、ペガサスは店内に再び突進した。だが、そこからがマライアの予想と違っていた。
ジョニィは、マライアがいた更衣室の前を、突風を巻き上げながら、突っ走っていっただけだった。
「な・・・・・なに?・・・あ・・アーッハッハッハ!外したのね!全く、これだからヘナチンな男ってダメね!」
ところが、再び空気を切る音が店内に聞こえ始めた。
「え?」
そして、マライアは叫ぼうとした。しかし、叫ぶ時間はなかった。次の瞬間、一斉に飛んできた剣が、更衣室を貫いた。中にいた人間が、串刺しになることは、想像に難くない。
- 「・・・・・・・・・・・」
カツ、カツ、とライダーはブティックの中を歩いていた。ついさっき、ンドゥールの死体に然るべき始末を施して、やっと追いついたところだ。
ライダーは、血液が流れてくる更衣室を見つけると、そのカーテンを開けた。
そこには、凄まじい体勢で串刺しになっているマライアの姿があった。
「・・・・・・どういう作戦をとったかは知りませんが・・・・ジョニィが勝ったようですね」
「ヒュー・・・・・・・ヒュー・・・・・・・・く・・・・ぞ・・・・この・・・ビチ・・・・クソ・・・共・・・が・・・・」
もう、何もせずとも死へと至ることは明らかだった。しかし、運が良いのか悪いのか、完全に急所を突ききれていなかったのだろう。
ライダーは、血の塊と、紫煙が薄らと立ち上る喉笛に、ナイフを突きつけた。
「質問に答えなさい・・・・・・・答えれば、すぐに楽にしてあげましょう」
「・・・・・・・・・・」
マライアは、何も答えなかった。だが、ライダーは続ける。
「貴方はアーチャーの仲間ではなく、自発的にこの行動を開始した・・・何故ですか?」
「ち・・・・が・・・・う・・・」
「違う?」
「そう・・よ・・・わ・・た・・・し・・・・たち・・・の・・・・意志・・・・じゃあ・・・ない」
「では、誰の意志だというの?」
-
「わ・・・たし・・・たち・・・・・・は・・・・・運命・・・の・・・・兵隊・・・・で・・・すら・・・な・・・い」
「具体的に言いなさい」
マライアの口から、血塊が吐き出される。そして、ごぼごぼとむせ込んだ後、さらにかすれた声で続ける。
「わ・・・わたし・・・・・たち・・・・は・・・・・・・みんな・・・あの・・・かた・・の・・・・・ど・・・・れい」
「誰?誰の奴隷だというの?」
「・・・・・・・・・・・・・復讐・・・・・・者・・・・・・・」
「アヴェンジャー?」
「・・・・・・・・・・天国・・・・への・・・・・・階・・・・・・・段」
「天国への階段?」
「・・・・・・・・・あの・・・方が・・・・・みちび・・・・・か・・・・れ・・・ゲハッ!」
喉に、血塊がつまったのか、これ以上ない苦悶の表情を浮かべると、マライアは口から大量の血液を吐き出した。
ビチャビチャと、ライダーの紫の頭髪に、黒く濁った血液が飛び散る。ライダーは何も言わずに、それを頭から被るだけだった。
「・・・・・・・・・」
ゆっくりと、ライダーはハルパーを、マライアの喉から離した。もう、必要なかったからだ。
「・・・・・・・誰・・・・?・・・・誰かがこの戦いを支配しているというの?・・・まあ、いいですわ」
ナイフをしまうと、ライダーは歩き始めた。
「さて・・・・・・ジョニィと合流しなくては・・・・・・・・」 -
ようやく、頭痛が引きはじめた。アーチャーは、頭を抱えながら、ゆっくりと公園に置いてあったベンチに尊大な姿勢で座る。
「・・・・・・・・・・・・・・・・この記憶・・・・・・・・そうか・・・・・」
アーチャーは、全てを理解した。何故なのか、ようやく分かった。自分に封印されていたものがなんなのか、ようやく分かった。
「・・・・・・・・すると・・・・私は斬らねばならぬのか・・・・行くしかないな」
「・・・・・・・早い話、ヘビーウェザーと無限の剣製が、反応を起こしているのだ」
『記憶ト記憶・・・・・・・・引キ合ウ・・・・・ナニガオコルカ?』
プッチ神父は、杖とホワイトスネイクの指示に従い、ゆっくりと歩いていた。視覚のDISCを抜いているからだ。
「何を見た・・・アーチャーは自分と向き合い、何を見た・・・・・それを調べねば・・」
プッチは、慎重に無機質な町を歩き続けていた。
そのときだった。聞き覚えがある声がした。
「・・・・・・・・待っていたぞ、エンリコ・プッチよ」
プッチ神父は声がした方を向いた。視覚は機能していないが、声は敏感に分かる。
「・・・・・・アーチャ。一体どうしたんだ?・・・・・・一体君は何を見た」
「・・・・・・・・なあに、こういうことだ。・・・・・トレースオン」
- 瞬間、プッチ神父の周辺に剣が現れた。
「・・・・・ん?」
視覚がないので、プッチ神父はそれに気が付かなかった。だが、自分に剣先が触れた瞬間、ようやくプッチ神父は気が付いた。
「な」
避けることもままならなかった。十本の剣が、プッチ神父の体を貫く。
「な・・・・・・ぐあああああああ!」
思わずプッチ神父はその場に転がる。そのせいで、さらに剣が深く突き刺さる。
「な・・・・・・・何をするんだ、アーチャー!?」
「知れたことを・・・・・・・」
いつの間にか、アーチャーの手には、偽螺旋剣が握られていた。
「ここで貴様を葬ることに決めた」
「なに!?」
アーチャーが、プッチ神父の元へ、歩み寄る。
「貴様はここで死なねばならない。そうしなければならないのだ」
-
「(バカな・・・・・アーチャーが私を殺そうとする・・・・?・・・いかん・・・・逃げなければ・・・逃げなければ)」
「これで終わりだ・・・・・・・さらばだ、エンリコ・プッチ」
アーチャーは、剣を持ち上げた。だが、プッチもスタンドに命じていた。
「ホワイトスネイク!私に視覚を戻せ!」
ホワイトスネイクは、プッチの眼球にDISCを差し込んだ。同時に、プッチ神父の目に光が宿る。
そして、プッチ神父はアーチャーの遥か後方空の彼方にかかっていた虹を直視した。
気が付いたときには、アーチャーの視界にプッチ神父はいなかった。剣の山に、新たに一本剣が増えていただけだった。
しかも、どれが増えた剣なのか分からない。
「・・・・・・くそ・・・・・逃げられたか・・・なら・・・虱潰しでいい・・・・・確実に殺す」
だが、アーチャーが再び呪文を詠唱しようとしたとき、平らな弾丸がアーチャーの顔前に射出されていた。今度は、避けることはできなかった。
アーチャーのこめかみから、鮮血が飛び散る。
「ぐう・・・・・・・また来たか・・・・来訪者よ・・・・」
アーチャーの上方には、天馬が飛んでいた。
「・・・・・・・・これで終わりにする!」
「何回やれば分かる・・・・・貴様一人で・・・・」
「あら、一人ではありませんわよ」
アーチャーは、振り向いた。視界が赤く濁っていたが、問題はない。
振り向いた先、そこには、ライダーが立っていた。
「マスターはいないようね・・・アーチャー、仕留めさせてもらいます」
-
「・・・・ジョニィ・ジョースター・・・貴様なら分かるだろうに・・何故気が付かない・・・・?」
「なんだと?」
アーチャーは、剣を鞘に納めた。そして、体から発する殺気を鎮めていく。ジョニィは、天馬を地上へと降ろした。
「・・・・・・たとえば、私達は・・・・・・初めからこの世界で戦っていたのか?」
「?」
「初めは、誰が誰と戦っているのか、それさえも分からなかったはずだ」
「・・・・・・・・・・・・」
ジョニィは、その言葉に何故か疑問を抱くことができなかった。
「・・・・・・また・・・・そうだな。バーサーカーのマスターは、別のマスターだったはずだ。違うか?」
ライダーもジョニィも、アーチャーの言っている意味が分からなかった。だが、分かるのだ。
分からなければならないのだ。
「あるいは・・・・・・・キャスターとそのマスター・・・そしてアサシン・・・一度死んだはずだ、何故生きている?」
そうだ。確か真アサシン達の計略にはまり、バーサーカーと自滅したはずだ。
「そして・・・ギルガメッシュ・・・・奴も一度消滅したはずだ・・・・何故敗北したものが、平然とこの世界で戦っている?」
そうだ。ギルガメッシュは、承太郎とセイバーのコンビネーションで、宝具の直撃を受けて消滅したはずだ。
「分かるだろう・・・・エンリコ・プッチよ・・・それが蘇った俺の記憶だ・・・この世界で繰り返される戦いの記憶・・・貴様はそれを蘇らせた・・・」
-
「・・・・バ・・・・バカ言うな!だとしたら、そんなことをできるやつがいるというのか!?」
「いた・・・・・今はもう死んだ・・・そのはずだった・・・・だが・・・生きていた」
一瞬、アーチャーの視界が眩んだような気がした。出血過多のせいだろうか。
「創世神・・・あれはもう滅びたはずだった・・・・・だが、その呪いは生きていた。繰り返される平行世界・・・人々に植え付けられる記憶・・・・その呪いだけが生きていた・・・
そして・・・・・・世界は繰り返され・・・最終的には・・・・理想的な世界・・・・・そうか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そうだったのか・・・・・・・ようやく全て一つに繋がったぞ!
貴様か!貴様だったのか!何をするつもりだ!貴様はなんの世界を作り上げるつもりだ!」
突如、アーチャーが激昂した。
「私達は・・・・運命の奴隷ですらなかった!奴の奴隷でしかなかった!」
「どうしたんだ、アーチャー!・・・・落ち着け!落ち着くんだ!」
「黙れ・・・・黙れ黙れ!」
その瞬間、アーチャーは剣を引き抜いていた。居合い斬りの要領―一一瞬の斬撃だった。
「・・・・・な・・・・に?」
ジョニィの臓物と血液は、宙を舞っていた。ライダーにも、そのさまはよく見えていた。
「な・・・・・・・アーチャー!不意打ちとはよくも!」
ライダーが、ナイフを持って跳躍した。だが、アーチャーは一言呟いただけだった。
「トレース・・・オン」
その言葉と同時に、ライダーの体を虹が貫いた。ただの虹だ、光が生み出す現象でしかない。
だが、その虹がライダーの体を貫くと同時に、ライダーの腹部から、数十本の剣が飛び出した。
「え・・・・・・・・?」
体内の微小な細菌を剣に作り変えたとライダーが気が付くことはなかった。
ほんの数秒の誤差もなく、マスターとサーヴァントは絶命した。
-
「・・・・・永遠に己の墓標を刻み続ける男・・・・死後も安息を求め続ける男・・・
永遠に楽園へ帰ることが叶わぬ神・・・・・・天国への階段・・・・666の暴君・・・・・
それとも・・・・また・・・・言峰・・・貴様らか・・・・・?」
「教えてやろうか?」
「そうだな。運命だ。オレだって運命の奴隷だ。テメーらもオレも、みんな雲の上で目の下に指をあてて、舌を突き出してるあのクソヤローの奴隷なんだよ」
「繰り返す、どこまでも、どこまでも、繰り返す。永遠に、どこまでも繰り返す」
「それだけだった。だが、違かったんだよ。繰り返してすらいなかった」
「アイツだ。この世界は、何百回も繰り返し続けてきた。戦って、死んで、戦って、死んで」
「だがよ、微妙に世界が変わり始めてやがった。少しずつ、世界が広がり始めた」
「その内、来なくてもいいやつまで現れやがった。消えなくてもいい奴まで消えやがった。ぶっ壊れたピアノが少しずつ調律されていくような光景だった」
「メイド・イン・ヘヴンつったか?そう、それだよ。お前が気が付いてるとおりだ。オレが戻した先の世界は、戻す前に存在していた世界を、記憶してたんだよ」
-
「オレだって面食らったさ。繰り返すだけでいいのに、変化を始めるんだもんな」
「けどなあ、その内気が付いた。それなら、この世界を繰り返した先に、何があるんだろうなってな」
「ヴァニラの願い・・・・蘇らせたい野郎がいる・・・・それも叶うんじゃねえだろうかってな」
「死者を蘇らせられるのは生者だけだ・・・だが・・・初めから『生きてる』世界なら、世話ねえよなあ」
「だが・・・・その内オレは気が付いたってわけだ」
「『なんだ、俺達の意志じゃなかった。初めっから、そういうシナリオだったんだ』ってね」
「はっ!何てことだよ!あの神父が天国へ行くのも、オレがこの世界に閉じこもるのも、全部あいつの計画通りだったんだよ!」
「だが・・・いまさらやめられなかった。ヴァニラは、そういう足掻き方しかできなかった」
「自分の主人のために、足掻く事でしか、ヴァニラは自分の存在を作りきれなかった」
「可哀相な奴さ。他人の為に足掻くことしかできなかった・・・自分の為に足掻く方法がなかった」
「オレとアイツは―似たもの同士だ。全然違うさ。性格も、本質も、何もかも」
「けどな、似てたんだ」
「さあ、終わりだ。この世界は終わる。そして、また同じ戦いが始まる。そして、聖杯により××」
頭部から血を流して、アーチャーはその場に倒れていた。
「・・・・ち・・が・・・・う」
もう、力は残っていなかった。
「俺は・・・・・・の・・・・方に・・・な・・・り・・・」
道の向こう、誰かが立っていた。全身に異様な装飾をした人間にも見えた。
「聖杯・・・・・・・の・・・・・泥」
そして、突然道路が口を開けた。アーチャーは、その穴に落下した。そして、アーチャーは粉みじんになって死んだ。
口が閉じると、その界隈の空気は完全に死んだ。
もう、何もなかった。何も。
-
「たとえば、だ。アーチャーよ。君は何をもって死者の存在を実証する?」
壊れた屋根から落ちる雨が、朽ちた机を静かに濡らしていた。プッチは、一段高い教壇から、静かに話していた。
アーチャーは、壊れた机の上に寝そべっていた。
「それは洒落事か?・・・感傷的な言い方をするなら・・・思い出やら・・・記憶・・・記録と言った方がいいか?そういうものだろうな」
屋根も仕切りもない懺悔室では、ホワイトスネイクが自分が今まで収集した記憶を整理していた。
『歴史トハ、記憶ノ積ミ重ネ。繋ガル記憶。思イガ、人ノ歴史トナル』
突如、何もない場所から声がした。
「だが、思いは然るべき人間が受け継がなくてはならない。人々の思いをかなえられる人間が」
骨が砕けるような凄まじい音がすると、そこに一つの口が現れた。そこから、一人の男が姿を見せる。
「この世界には、偽善者が多すぎるとは思わねーか?ああいう奴は自分のことで手一杯だ。願いをかなえることはできねえ」
教会の隅、そこに一人の男が立っていた。彼の全身には、異様な装飾が施されていた。
「英雄だけだ・・・・この世界の望みを叶えることができるのは、この世の全てを飲み込める英雄だけだ。そうだろう、わがマスター」
教会の門に、金髪、金の鎧の男が立っていた。
そして、磔のキリスト像の下に、同じく、金髪、金の服、金のスタンドの、その男が立っていた。
「そうだ・・・・・・英雄だ。完璧なる世界に必要なのは、英雄だ。さあ、諸君、行こう。完璧なる天国の刻のために」
「そうだ・・・・行こう、DIO」
そして、プッチ神父は、彼の永遠の親友、DIOの傍らに立つ。
割目し覚悟せよ数多の残骸。
汝等が目にするは完璧なる時計仕掛けの世界。
黄金なる守護神と装束に身を包んだ、汚れなき楽園の具現。―ここに。
終わりにして絶対不落の、真なる王が存在する。