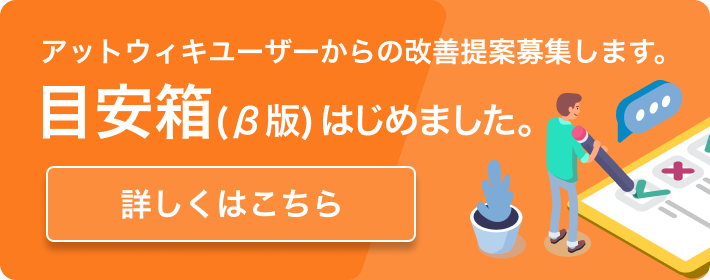ジョジョの奇妙な聖杯戦争
VSギアッチョ
最終更新:
匿名ユーザー
「……」
汽笛が、海上に轟く。
「よお、ギアッチョ」
「おう、メローネ」
暗殺チーム九人衆の二人、ギアッチョとメローネは、お互いの姿を確認すると、挨拶を交わした。
「ペッシはどうした?プロシュートの野郎がいないから、まだ落ち込んでやがるのか?」
「ああ。リゾットとプロシュートは先に上陸しているからな・・・・ホルマジオとイルーゾォは空路で向かってる。一箇所にあつまって移動すると危険だからな」
「そうかい…へ。要するに、そのサーヴァントとか言うやつを皆殺しにしちまえばいいんだな?」
「そうだ……だが、あの二人が手こずっているくらいだ。スタンド使いに匹敵する連中だな・・・この聖杯戦争とやらを制するには」
ところが、最後までギアッチョはメローネの話を聞いていなかった。突如ギアッチョはメローネに尋ねた。
「なあ、なんで聖杯戦争って言うんだ?」
「あ?そりゃ…(しまった)」
「戦争ってのはよお、普通国家単位の戦いの時に言うんだよなあ。でもこいつは、国家どころか十数人しかいねえじゃねえか。
あ?くそ!何が戦争だよ!聖杯争奪戦って言えばいいじゃねえか!クソ!クソ!クソ!わけわかんねぇよ!」
「お、おい、ギアッチョ、落ち着け!」
突如ギアッチョは、船の柵を叩き始めた。その姿を見て、メローネは、ギアッチョに掴みかかった。
「クソ!クソ!ふざけやがって!なめてんのか!」
「や、やめろギアッチョ!」
ところが、メローネがギアッチョに掴みかかった瞬間、ギアッチョに殴られた柵が、崩壊した。
「あ!?」
メローネは、すんでのところで踏みとどまったが、そのままギアッチョは海に落下していった。
「お、おい!ギアッチョ!」
ギアッチョの影が海に消えるかどうか、その瞬間だった。船が激しく揺れた。まるで氷山にぶつかったかのように、停止した。
「うお!なんだ!?……ま、まさかギアッチョ・・・てめえ」
船の真下の海水が、完全に凍りついていた。そのせいで、船は動けなくなっていた。
次の瞬間、真っ白な影が海上に現れた。
「…なんだろうが関係ねえ。貴様ら全員に、この俺の戦争を見せてやる」
そのまま、氷の橋が、海上に作られた。その上を、白い影が滑るように走っていく。
「はは・・・ギアッチョめ、やる気だな。……さて、どうしたものか。…俺もこの氷の上を渡っていくか。陸も近いしな。
おい、ペッシ!何やってやがる!お前のアニキのところに行くぞ!早く用意しやがれ!」
「……」
アーチャーは、埠頭に佇みながら、静かに海の果てを眺めていた。
『アーチャー。君に悪い知らせと良い知らせがある。どちらから聞きたい?』
『手短に言いたい方から言え。どちらにしても結果は覆らない』
『そうか。では、定石通り、良い知らせから言おう。我々の協力者が、この町に向かっている』
『役に立てばいいのだがな……で、もう一つは?』
『こちらが動くということは、敵も動く時期ということだ。敵の密偵を捕まえ、情報を奪った。敵の精鋭が、近づいているらしい』
『……どこからだ?』
『空路、海路・・・両方から・・・・アーチャー。どこへ行く?』
『敵が戦場に上がる前に、進路を絶つ。それが戦闘の定石だ。上がる場所ばおよそ絞り込める』
『…そうか。ではこのDISCを受け取りたまえ』
『これは?』
『敵の密偵の記憶だ。どんな手段で上がってくるのか、おおよそ記してある。…私も後から行こう』
『そうか……感謝しよう、エンリコ・プッチ』
情報通り、赤い炎の絵が描かれた船が、およそ港から距離1500メートルの地点に近づきつつあった。
「情報なら…あれは偽装。貨物船のふりをして、実際は数人の人間を運ぶためにわざわざチャーターした船・・・一般人は皆無か」
と、突然その船が動きを止めた。それを確かめると、好機と見て、ゆっくりと剣を取り出した。
「悪く思うな……これは戦争だ」
アーチャーは、それを弓にあて、引き絞った。そして、一言呟くと、その剣に魔力を収束させる。
と、剣の形状が変化する。
「赤原猟犬<フルンディング>……ゆけ!」
次の瞬間、一筋の赤光が、海上を走った。
赤い閃光は、真っ直ぐに前方の貨物船へ海面を穿ちながら進んでいった。そして、貨物船の横で軌道を変え、そのまま船体を貫いた。
次の瞬間、激しい爆風が穿たれた穴より巻き起こる。おそらく、エンジン部分に命中したのだろう。
その一撃が、完全に船の動きを殺した。船は、船体から火を噴きながら、不安定に揺れ始めた。だが、沈没や、崩壊するほどのダメージではない。
「・・・これでよし。後は、公僕どもが適当にあしらってくれるだろう」
適当にダメージを与えさえすれば、嫌がおうにも警察が動き出す。イタリアーノマフィアならば、どちらにしても警察に任せれば、何も問題はない。
「目的は果たした・・・・・次は・・・・空港か」
アーチャーが燃え盛る船を尻目に、踵を返し、そのまま港を離れようとした。
その時だった。
何か、アーチャーの聴覚に、金属音に近い音がした。
「・・・・なんだ?」
シャッ、シャッ、と、磨きぬかれた刃金同士が擦れる音が、アーチャーの意志に関係なく、アーチャーの聴覚に飛び込んでくる。
「・・・・・・・・なんだ、この音は!」
咄嗟に、アーチャーは船の方を振り向いた。そして、息を呑んだ。燃え盛る船のより、白い影が現れたからだ。そしてそれは、海上を歩いていた。
いや―――違う。音により、影の動きの軌道により、アーチャーは気がついた。走っているのではない。あれはまるで―――そう、スケートだ。
「先手必勝か! やってくれるな! だが、生憎数分差で俺が飛び出すのが先だったようだな。
貴様の姿は完全に確認した! この俺の氷の世界で溺れさせてやるぞ!」
「バカな・・・・・どういう能力だ!?」
アーチャーでも、その男がどのような能力を行使して、海の上を走るという芸当を行っているのか、即座に判断することはできなかった。
「遅いな!早く避けたらどうだ!?」
オリンピッククラスのスピードスケーターも真っ青になる加速で突撃していたギアッチョは、突如跳躍した。その跳躍は、一飛びで自分とアーチャーとの間の、50mの距離を縮める。
「なに!」
「ふん、完全にとった!」
ギアッチョは、鋭利な刃物を思わす白い氷の鎧を纏った腕を、アーチャーに振り下ろした。
「くらえぃ!」
「そうみすみすと!」
アーチャーは二刀剣を取り出し、それを交差させてギアッチョの腕を受け止めた。
と、アーチャーは息を呑んだ。剣と腕がぶつかり合う瞬間、火花のようなものが散ったからだ。
「(火花!? ・・・・・・・どういう力だ!?)」
「ほお、最低限の戦闘センスぐらいは持ち合わせているようだな」
「く・・・・・戦いの最中に!無駄口ぉお!」
アーチャーは交差させた剣を振り回し、ギアッチョを放り投げた。さすがにサーヴァントの力の前には、ギアッチョも成すがままに放り投げられる。
「うおお!?」
地面に凄まじい力でギアッチョは叩きつけられる――と思った。しかし、ギアッチョが地面に叩きつけられる瞬間、何かの力が働き、ギアッチョの体は地面を滑っていく。
勿論、ダメージになったとは思えない。
「・・・奴が滑った場所に、氷が張っている・・・それにあの火花・・・火花というよりは、砕けたガラスのような・・・
・・・大凡の見当はついた。だがこれは・・・・少々苦戦しそうだな」
「く・・・・・やってくれるな。情報によると、アーチャーとか言うそうだな!」
ギアッチョは、足のスケートで氷上にて体勢を立て直し、アーチャーに叫んだ。
「・・・・・・貴様の情報も思い出した。確か、ギアッチョという男だったな。どうやら貴様のスタンド能力は・・・氷を操る能力のようだが」
「気づくのが遅いんだよお!自分の腕を見てみろ!」
ハッ、とアーチャーは自分の両腕を見た。両腕には霜が走っており、気がつけば、動かなくなっていた。
「な・・・・・・なに?!」
冷気を感じる暇さえもなかった。霜が走っていると言われて、そういえば冷たい気もする、と気がついた程度だった。
無論、その程度の冷気だったのではない。そう感じるしかないほどの速攻性だったのだ。
「ははははは!どうだ、これが俺のスタンド、『ホワイトアルバム』だ!さあ、どうやって俺を倒す!?貴様の覚悟を見せてみろ!」
ギアッチョは、シャッ、シャッ、と刃金が擦れる音を立てながら、アーチャーの周囲を回り始めた。あざ笑うかのような様相のギアッチョの全身スーツからは、氷の結晶が時折振り落とされている。
「(く・・・・・つまり、打撃を仕掛けるのは、ほぼ自殺行為ということか・・・! 考えられるのは・・・凍る暇も与えずに、叩き潰す!)」
「一つ言っておくが、凍る暇も与えずに叩きのめす、というのは、出尽くされた手段だからなあ、お勧めしかねるなあ」
ギアッチョは、少しも速度を緩めずに、即席のスケートリンクと化した地面を滑りながら、せせら笑いとともにアーチャーに告げた。
「な・・・・・・に!?」
「俺の力をなめるな、と言っているんだ。貴様が行うあらゆる攻撃を防ぐ自信が、俺にはある」
そういって、少しずつギアッチョは距離を詰め始めた。
「(斬るのは不可・・・・・どうすればいい?・・・捨て身で仕掛けるか?・・・愚か者め。それは阿呆のやることだ。
勝算なき覚悟は、覚悟ではない。ただの蛮勇だ)」
「はっはっは!どうした!貴様が仕掛けないのなら、こちらから仕掛けるぞ!」
再びギアッチョが跳んだ。今度は、問答無用で掴みかかる形だった。
「くう・・・迎撃せねば・・・ぐ・・・しかし腕が動かない・・・だと!?」
易々と、ギアッチョの接近を許す。そして、その腕がアーチャーの首を掴んだ。
「があっ!?」
「取ったぞ、アーチャー!このまま貴様の首を凍らせ、その頭をカキ氷のように叩き壊してやるぞ!」
ギアッチョの、白い鎧に覆われた腕が、アーチャーの首を締め付ける。そして、その腕から、氷が伝っていく。
「はははは! そのまま貴様の脊髄と血管を一本のアイスバーにして、ポキリとへし折ってやる!」
氷が、アーチャーの首まわりを覆っていく。だが、その攻撃に対して、アーチャーは、ギアッチョに静かに言った。
「・・・・・いい・・・のか? ・・・・ここにいて?」
「いいのか、だと!?仲間のことを言っているなら、貴様に心配される理由はない!ついさっき脱出を確認した!!悪あがきは止すんだな!」
「ち・・・・・・が・・う」
「あ?てめえ、わけわかんねんだよ! 何が言いたいのか、はっきり言いやがれ! むかつくんだよこんちくしょう! ぶっ殺すぞ!」
次第に荒れ始めたギアッチョに対し、かすかに笑みを浮かべながら、宣告した。
「・・・・・・海を・・・・・見てみろ」
「あ? ・・・・・・・・なにぃ!?」
ギアッチョは、ようやくアーチャーの言葉の意味を理解した。ついさっき、アーチャーに機関部を破壊された貨物船が、炎上しながら港に突っ込んできた。
「こ・・・・・・・これを待っていたのか!?」
アーチャーは、鼻先で笑っただけだった。ギアッチョはアーチャーにとどめを刺そうと冷気の出力を上げたが、時は既に遅し。
地獄の炎を満載した船が、そのまま二人を飲みこんだ。
衝撃が、二人を弾き飛ばす。そのまま二人は、崩壊した埠頭より、海に落下する。
「うごお! これを狙っていたか!」
船から零れ落ちる燃え盛る貨物が、海の中を混沌の渦にする。その状況の中、気がつけばギアッチョの腕はアーチャーより離れていた。
「ぐう! ・・・・・・・・・・・・・・? ・・・・・・・あれは?」
その時、海中で揉まれるギアッチョの背中に、アーチャーは確かに見た。
水泡が渦巻く海中でもしっかり確認できるほど、大きな水泡が立ち上る点を。
「(・・・・・・あれだけの完璧な氷を纏ったスーツ・・・・だが、口元から空気が流れる様子は見えなかった・・・・読めたぞ!)」
咄嗟に、なんとか動き始めた右腕で、アーチャーは剣を握ろうとした。だが、そこで思いとどまった。
「(あそこがあの氷の牙城を突き崩す唯一の点ならば、乾坤一擲の一撃で決めなければ、もう手はない・・・)」
アーチャーは、海面へと向かって泳ぎ始めた。
「(だとするなら・・・・・ただ叩き込むのみ!)」
一方ギアッチョといえば、激しい渦に加えて、自分が作り出した氷の中でもがいていた。
「くそお!こんな戦法でやられるとは!」
ギアッチョは、海上にアーチャーが向かうのを見ると、上に泳ごうとしたが、逆に自分が暴走させた氷の中では、動く事もままならない。
「ええい!」
自分の周辺の氷を解除し、足元に氷の足場を作り出した。
「俺から逃げられると思うな! 機動性! 破壊力! 防御力! 全てにおいて俺は貴様を上回っているぞ!」
そして、海面からギアッチョは顔を出した。
――I am the bone of my sword.――
「くそ・・・ふざけやがって・・・・奴め」
――Steel is my body,and fire is my blood.――
ギアッチョは、散乱したテトラポットを伝いながら、海上に上がった。
―I have created over a thousand blades.―
「どこだ!俺から逃げられると思うな!」
―Unknown to Death.―
再びギアッチョは滑走を始めた。その滑走の後方は、氷に覆われる。
―Nor known to Life.―
「どこだ・・・この時間だ、どこに逃げることができる!?」
―Have withstood pain to create many weapons.―
だが、瓦解した船の炎の海のどこにも、アーチャーの姿は見受けられなかった。
―Yet,those hands will never hold anything.―
・・・・・・・・・・・・
「くそ!どこだ!どこに隠れることができる!?」
―So as I pray,"unlimited blade works".―
「・・・・・・・ようこそ、氷を従えし男よ。この剣の丘へ」
その時になって、ようやくギアッチョは、アーチャーがどこにいるのか気がついた。
アーチャーは、燃え盛り、天に船首を向けた船の先に立っていた。先程から耳に入ってきた耳障りな言葉が、アーチャーの呪文だったと、その時になってギアッチョは気がついた。
しかし、アーチャーの姿を見て、ギアッチョは息を呑んだ。アーチャーの服には、火が引火していた。だが、それは不測の事態ではなく――。
「自分の体に火をつけることで、俺の氷を溶かしたか―」
「ああ・・・・そろそろ勝負をつけることに決めたからな。覚悟はできたか?私はできている・・・いくぞ――全方位投影開始!!」
アーチャーの周辺に、次々と武器が投影されていく。そして、ゆっくりと回転を始め、それがアーチャーが必要とする数まで投影された瞬間、アーチャーは叫んだ。
「 ―無限の剣製― その身でたっぷりと味わうがいい!」
一斉に、剣の嵐が、敵を切り裂くために、飛び立った。だが、ギアッチョもまた、無抵抗ではない。
「そんな攻撃でこの俺が負けるとでも思ったか!?ならば俺も最高の技で出迎えてやろう!『ホワイトアルバム・ジェントリーウィーブス』!」
その瞬間、ギアッチョの周辺の空気が、-273・15℃、つまり絶対零度を迎えた。この、もはや冷たささえも感じることは不可能な世界で、動ける物体はない。
そして、酸素さえも、凍りつく。完全なる防御障壁が、ギアッチョの周辺に構築される。その障壁に向かい、幾多数多の剣が突進する。
「無駄だあ! 貴様の攻撃は、俺を仰け反らせることもできないんだよお!」
「・・・・・・承知の上だ。だからこそ!」
剣は全て、ギアッチョの鎧に触れる寸前で静止する。だが、アーチャーは全く怯まない。それどころか、さらに追加で投影を行う。
「だから無駄だと! 貴様の攻撃は、絶対に俺に触れる事すらできんのだ!」
だが、それでもなおアーチャーの投影は停止しなかった。ギアッチョの周辺空間を埋め尽くす数の剣が、さらに投影される。
「(バ・・・・・バカな!?こいつ・・・・何をする気だ・・・・・グウ!?)」
突如、ギアッチョは息苦しさを覚えた。理由は明白だ。これだけの数の剣を止めるには、ギアッチョの全方位の空気を凍らせなければならない。つまり―。
「(酸素が補給できない!? バカな! それが奴の狙いか!?)」
とても、ギアッチョにはそうは思えなかった。だが、そうだとするならば―。
「(酸欠で俺が倒れるのは必至・・・・これを狙って!?だ・・・だが・・・・・一点だけ・・・空気が通れる道を作れば!)」
ギアッチョは、首の後ろ、空気穴の後方の空気だけを調節し、そこに空気の抜け道を作り上げた。それが、ギアッチョ最大の誤算だった。
「その道を・・・・ずっと待っていた!」
炎をまとったカラドボルグⅡを持ち、いつのまにかアーチャーはギアッチョの後方に移動していた。
「貫くは一点! ゆけ! 逆螺旋の剣よ!」
「なあ!?」
アーチャー自ら、全身に炎をまとって、ギアッチョに突進をかけていた。そして、ギアッチョは一歩も動くことができなかった。周辺では、無限の剣製がギアッチョを貫かん、と滞空しているからだ。
「ぬおおおおおおおおおお!」
どちらの咆哮だったか、それは分からない。だが、一つだけ分かっていることがある。
その一撃で、勝負がついたことだ。
ゆっくりと、火炎と冷気を晴れてゆく。
傍目から見て、アーチャーの剣が、ギアッチョの首を貫いたように見えただろう。
だが、それは間違っていた。
逆螺旋の剣は、空気穴の位置で、凍らされていた。
「・・・・・・くっくっく、正直どうなることかと思ったが、俺が一瞬早かったようだな!空気穴は塞ぎきった!」
確かに、アーチャーの一撃は、空気穴を突破し、ギアッチョの首の皮膚一枚を切り裂き、あと少しで脊髄を傷つけられるところまできていた。
だが、そこまでだった。アーチャーの乾坤一擲の一撃は、ギアッチョを貫けなかった。
「はははは!これでお前は完全に射程圏内だ!ジェントリーウィープスで凍らせ殺してやる!」
「できるのならやってみろ?」
「・・・・・・・・なに?」
「やってみろ、と言っているのだ。できるのなら早くやればいい。だが、この剣は貴様の皮膚まで触れている。鉄の熱伝導率は、かなり高いぞ?」
早い話、アーチャーを凍らせれば、そのままギアッチョも絶対零度で凍りつく、ということだ。いや、ギアッチョの能力の性質上、そうはならないかもしれない。だが―。
ギアッチョの首筋で、嫌な汗が一滴流れた。――これは駆け引きだ。一瞬で、勝者と敗者が逆転する最後の勝負だ。
「は、はん!だが、どちらが先に凍るのか、それは明白だろうが!第一、その剣はもう、押す事も引くことも叶わないだろうが!」
「そうだな・・・・・では、離すとしようか」
あっさりと、アーチャーは自分の剣を手放した。
そのまま、アーチャーはジェントリーウィープスの射程から後退していく。
「な・・・・・・・貴様、なんのつもりだ?勝負を捨てたか?」
「そうではない・・・・・・・・・・これが最後の攻撃だ」
「な・・・・・・に・・・・・?」
その時、ギアッチョは首筋が何故か熱くなるのを感じた。
「・・・・・・・己が作り出した氷の海で溺死しろ。・・・・・・『壊れた幻想<ブロークンファンタズム>』!」
はっ、とギアッチョはようやく気がついた。あのとき、船を爆破したあの攻撃と、全く同じ攻撃―つまり―。
「し、しまった!この剣自体が爆弾か!?」
ギアッチョは、その剣を引き抜こうとした。しかしその剣は―ギアッチョの言葉を借りるなら、『押す事も引くことも叶わない』。
「こ・・・・・こんなのありかよ!?そ・・・そうだ!ジェントリーウィープスを解除しねえと!」
――DUS・ENDE。一斉に、阻むものをなくした剣が、ギアッチョに降り注ぐ。それが最後だった。
「げぶ!」
ヘルメットの中で、ギアッチョは吐血した。そして、ゆっくりと両膝をつき、その場に崩れ落ちた。
そして、ブロークンファンタズムが発動した。
そして、轟音の後、ギアッチョの姿は、激しい閃光と、壊れた幻想が、包み込んだ。
ギアッチョの白いヘルメットが、アーチャーの足元へ転がってきた。アーチャーがそれを踏み砕くと、春の日に作られた季節はずれの雪のように、溶けて消えた。
「・・・・・・終わったか」
爆心地を眺めて、アーチャーは呟いた。いくら氷の障壁で身を守ろうとも、零距離でブロークン・ファンタズムを受けて、生きてられる理由はない。
「・・・・・今更空港に行っても、無駄足か・・・だが、半分は目的を果たした。退くとしよう・・・」
アーチャーは踵を返し、その場から去ろうとした。そうしようとした。だが、アーチャーは再度、爆煙が晴れ始めた爆心地を眺めた。
「・・・・・・その覚悟は、戦士として、敬意を表するに値するがな」
ギアッチョは、まだそこに立っていた。全身を剣に射抜かれていたが、それでもなお、生きていた。
「・・・・へ・・・・・へへ・・・・・一瞬差だったけどよお・・・・・・剣を引き抜いて・・・氷で防御するまで・・・・へへ・・・・・俺の・・・・勝ち・・・だ」
だが、時間の問題であることは明白だった。何が明白であるか―いまさら語るまでもない。
「・・・・・・よ・・・・・よくもやってくれたな・・・・・・・・・アーチャー・・・・・・いま・・・・殺してやる・・・・ホ・・・・ホワイトォ・・・・アルバム・・・・
あ・・・・・?・・・・・は・・・・・早く・・・・・・・発動しろよ・・・・・・・」
「・・・・・・死を前にしてもなお、死ぬためでなく、勝利の為に戦う貴様に、敬意を表しよう」
今一度、アーチャーは剣を弓に番えた。
-
「赤原猟犬<フルンディング>・・・・・いけえ!」
「ジェ・・・・ジェントリー・・・・・・・ウィープス・・・・・・・」
だが、一切の余力が残っていなかったギアッチョのスタンドパワーでは、自分の体に霜を降りかけるのが限界だった。赤原猟犬は、一直線にギアッチョの心臓を貫いた。
噴き出す血もなかった。ただ、心臓を貫いた一撃を見て、ギアッチョは虚しく呟いた。
「ああ・・・・・・・・くそ・・・・・・・ここで・・・・・・・終わりかよ・・・・・・・・
メローネ・・・あとは任せた・・・・・・すまねえ」
今度こそ、ギアッチョは永遠の氷の世界へと、崩れ落ちていった。
「・・・・・・・・・・・・」
何も言わず、アーチャは崩れ落ちるギアッチョの姿を眺めていた。
ギアッチョの体を覆った霜―――それは、死化粧のように、煌き、輝き、そして消えていった。
-
「・・・しかし、これに加えて四人か・・・・」
大地に打ち立てられた剣の前で、アーチャーは呟いた。
「既に敵は活動を開始している、と見るのが打倒か・・・・・いや、既に戦いは始まっているのかもしれんな・・・・
・・・・・・・・・聖杯戦争か」
そうだ、これは戦争なのだ。強者が生き残り、敗者が死に絶えるのが戦争の世界なのではない。それも一つの結果にすぎない。
戦争の唯一つの事実は、生き残ったものだけが生き残り、死したものだけが死ぬ――それだけだ。
「生き残ることなぞ、元より望んではいない・・・・我が墓に、勝利も、栄光も、理解も、何もいらない」
アーチャーは、次なる戦場へと、歩みを進めていった。
「我が墓標は、血潮に濡れた剣だけだ」